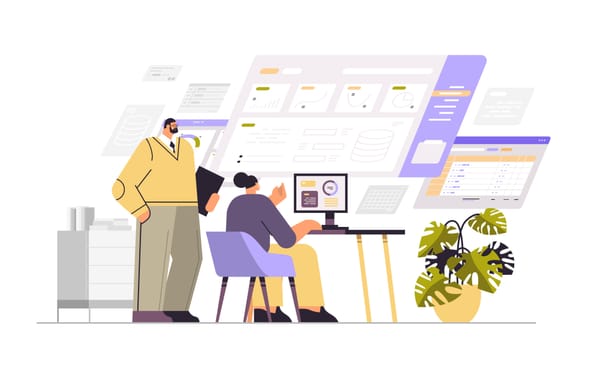トヨタ出資の配車企業グラブ、コロナ禍でハードランディング必至か
グラブとゴジェックは長期に渡る資金燃焼の末に、どうやって生き残るかを思案している。その一つの手段が合併だ。だが、両者は非常に多くの株主を抱えており、その同意を引き出すだけでも、不可能な仕事のように思える。

ファイナンシャル・タイムズ紙の9月の報道によると、グラブ(Grab)の共同創業者であるアンソニー・タンは地域の強力なライバルであるゴジェック(Gojek)との停戦を呼びかけるよう、孫正義から圧力をかけられていたようだ。
ライドシェアを展開するゴジェックとグラブは、新型コロナのパンデミックの中で資金を失い続けていることが、協議再開要請背景にある。FTによると、これまでの合併協議は、ソフトバンクの反対もあって停滞していた。しかし、今では、ソフトバンクの創業者でありCEOの孫がこの取引を支持しているという。
以前、情報筋はFTに、孫はライドシェアが独占産業になると確信しており、最も多くの現金を持っている会社が市場を独占するだろうと話していたと伝えていた。しかし、ゴジェックは、最大市場インドネシアに堀を築き、弾力性のあるライバルであることが証明された。
シアトルに拠点を置く調査会社PitchBook DataのアナリストAsad Hussainは、合併は「グラブとゴジェックの収益性を大幅に加速させる可能性がある」とFTに語っている。しかし、ロンドンに拠点を置く調査会社Fitch SolutionsのテクノロジーアナリストKenny Liewは、規制当局がこの取引を承認する可能性は低いと述べたとFTは報じている。「多くの経済が苦境に立たされている今、雇用が削減される可能性が高いことを考えると、合併は規制当局の支持を得られないだろう」。
これに対し、先週、ブルームバーグは東南アジアで最も価値のある2つの新興企業は、数ヶ月間の議論の後、定期的にZoomで会議を進めており、合意に向けて進展していると関係者の談話を報じた。
報道によると、両社がすべての事業を統合するのか、それともグラブがインドネシアのみでゴジェックの事業を買収するのかが大きな争点となっている。グラブの最高経営責任者であるタンは、取引後に支配権を残した形で、ゴジェックのインドネシア事業をグラブの子会社として運営できるような狭い範囲での買収を希望している。この取引形態の場合、タンは自身の株式の希薄化にも直面することはない。ゴジェックの株主は、東南アジア全域での合併を支持しているが、グラブの最大の投資家である孫は、ゴジェックの株主と一部の地域に限った取引をしたいと考えているとされる。
今回の協議では、タンと日本の億万長者との間の緊張関係が強調されている。グラブはフードデリバリーやデジタル決済にも進出しており、東南アジア向けのオールインワンの「スーパーアプリ」を目指している。しかし、同社の損失は孫正義や他の支援者にも影響を与え始めている。特にソフトバンクの支援を受けたWeWorkの破綻や、地域の企業を襲ったコロナウイルスの大流行の後では、同社の損失は深刻なものと受け取られている。
FTとブルームバーグの両者の報道とも、情報源はグラブ寄りのものと推測される。今年の2月にも、米テクノロジーメディア「The Information」が、グラブ側の情報源をもとにして両者の合併交渉を報じたとき、ゴジェック側は報道の内容を否定した。両者をめぐる報道は常に混乱しており、どちらが上手くゲームをプレイしているかについて相反する情報が流布していた。
つまり、ステークホルダーの誰かがメディアを利用して、情報戦を展開していると見ていいだろう。激しい競争にさらされている金融系メディアに不確実な記事を書かせるのは、そこまで難しいことではない。このようなノイズの多い状況では、報道を信じてはいけない。
確かなことは、金遣いの荒いグラブと保守的なゴジェックの争いは、COVID−19というブラックスワンによって、均衡点に到達したということだ。米国でギグワーカーの正規雇用をめぐる訴訟が始まり、ギグ・エコノミーのピークアウトが印象付けられた。配車や料理宅配のようなギグ・エコノミー企業は、多くの場合、黒字化しない可能性が浮上し、ギグワーカーを正規雇用した場合には、事業の持続可能性は無いに等しい。これは、東南アジアにそのまま当てはめられるわけではないが、重要なゲームスタッツなのは間違いがない。
ギグ・エコノミーの行き止まり
行き止まりにぶつかった両者は、財布の中身は好ましい状態ではない。企業価値のドラスティックな改訂なしでは、新しいエクイティ・ファイナンスにはありつけないだろう。COVID−19が早期に収束しない限りは黒字化も難しいだろう。
2018年にUberが東南アジア市場から撤退した後、Uberが27.5%の株式を取得した(現在はそこから一定程度希釈化している)グラブは、この地域を代表するシンガポールの配車企業だ。ソフトバンク、米ヘッジファンドのタイガー・グローバル、トヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループ、滴滴出行、衆安保険などが出資しており、推定企業価値は140億ドルに上るとされている。
一方のゴジェックはインドネシアの企業で、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピンでも事業を展開している。評価額は100億ドルで、グーグル、中国のテンセント、シンガポールの政府系ファンド・テマセク、三菱商事、三菱自動車、傘下の金融子会社にはフェイスブックと米決済サービス大手ペイパル、などの有力な出資者がいる。
当初、ソフトバンクが両社の合併を推進しているとの報道が浮上したのは、COVID−19が市場に大きな影響を与える前の3月のことだった。当時、両社の間では2年前から協議が行われていたとされていたが、緊急性はなかった。
しかし、昨年のWeWorkの破滅的な失敗を受けて、ソフトバンクが空売り投資家やアクティビストの餌食になるのを避けるために投資先の売却や統合を進めていることを考えれば、そこに緊急性が生じるのは自然なことだろう。ソフトバンクの債権は明確なジャンク債の範疇にあり、一部の格付け会社は格付けの対象から外している。日本の証券会社が高齢化した金融に疎い日本の富裕層への力強い営業力を誇っても、社債を発行できないのなら意味がない。また似たような危機が訪れたとき、プライベートエクイティのアポロが3月のときのように空売りを仕掛けてきたら、次こそ債権は紙くずになるかもしれない。
今年3月、ソフトバンクGは負債の返済のために410億ドルの資産を売却すると発表した。最も注目すべき売却は、今年9月13日に行われたArmのNvidiaへの400億ドルでの売却が確定したことだが、この取引が規制当局の承認を得られるとは考えづらく、最長18ヶ月の審査の後にすべてが水泡に帰す可能性が高い。
ソフトバンクGは手元流動性を必要としており、その他のさまざまな手段を試すことだろう。ある時から歯車が狂い始め、大量の資金を燃やし続け、それを日中韓の投資家のマネーで補い続けてきたグラブは、最右翼の位置にあるはずだ。
一方、グラブはアリババとの間で、約30億ドルの投資を確保するために、新たな資金調達を試みているとブルームバーグは最近、報じた。アリババは、ソフトバンクを筆頭投資家としている。
両者はインドネシアの電子商取引企業であるトコペディアの取引で協力関係を発揮したことがある。ライバルのテンセントから投資を受けようとするトコペディアの方針に筆頭株主のソフトバンクが圧力をかけ、最終的にトコペディアは70億ドルの企業価値でアリババとビジョンファンドからの11億ドルの投資を受けることになったと報じられている。
このような協力関係は、インドのSnapdealやPaytmなどでも効力を発した。両者ともソフトバンクかアリババが会社の実質的な支配権を手にしていた会社だ。グラブもまた同じような状況下に置かれているだろう。
ブルームバーグは、アリババの出資により、アリババが過半数の株式を保有しているEコマースサイトのLazada Groupとグラブが提携する可能性もあるとも報じた。このような可能性は、Lazadaが東南アジアの多くの国でeコマース市場をリードしていることを考えると、独占禁止法上の問題をさらに高めることになると考えられる。
アリババが30億ドルをグラブに投資したとすると、同社が調達した金額は131億ドルになる。ベンチャーキャピタルは、新規株式公開であれ、非公開売却であれ、どこかの時点で出口を出さなければならないが、グラブの場合はもう一つ圧迫要因がある。それは、2018年のUberとの取引条件だ。2023年半ばまでにエグジットしなければならず、それがかなわないならば、20億ドルをUberに支払わなければならない。グラブには時間がないため、IPOの可能性がある前にゴジェックと合併することは、重要な意味がある。
6月、グラブは成長が鈍化する中、コスト削減のために人員を5%削減すると発表した。TechCrunchによると、一部の市場でグラブの配車事業の流通総額(GMV)が2桁減少していることに伴い、同社のライドハイリングドライバーの収入は2020年4月に2019年10月と比較して約2桁の割合で減少しているという。3月から4月にかけて、14万9,000人以上のグラブのドライバーがオンデマンド配送の実行に切り替えた。
東南アジア市場を制する鍵は、GDPの4割を占めるインドネシアだ。インドネシア以外では、インターネットサービスは一定の規模に到達せず、確かな収益性を生み出すクリティカルマスに到達しない。
グラブはこのような市場構造を捉えることをせず、インドネシア以外の小さな市場を押さえることにたくさんのお金を使ってきた。マレーシア、シンガポール、フィリピンなどだ。

主戦場のインドネシアはゴジェックの庭であり、ゴジェックの創業者はジョコ・ウィドド政権で大臣職に抜擢された。この市場ではグラブは「お客さん」に過ぎない。インドネシアではドアは誰にでも空いている。しかし、しばしば歓迎されないことがある。グラブはデジタル決済業者の認可を中銀から受けることができず、それを取得した地場華人財閥リッポーグループの決済ビークルOvoへの投資を通じた参入を余儀なくされた。
そのゴジェックもまた、7月に社員の約9%に当たる430人を解雇すると発表した。レイオフとともに停止した事業は、自宅にマッサージ師や清掃員を派遣するサービス。社会的距離を保つのが困難なため、継続不能だと判断したという。
合併の障害
グラブとゴジェックは長期に渡る資金燃焼の末に、どうやって生き残るかを思案している。その一つの手段が合併だ。だが、両者は非常に多くの株主を抱えており、その同意を引き出すだけでも、不可能な仕事のように思える。
ソフトバンクは、以前、インドの電子商取引の2強のスナップディールとフリップカートの合併の仲人を取り持ち、失敗したことがある。ソフトバンクはスナップディールに多額の投資を行い、筆頭株主となったが、スナップディールが追加出資を断ると、ライバルのフリップカートに大量の資金注入を実行した。かなり強引なプロセスを踏んだ合併交渉は、あまりにも多い両者の株主の間でコンセンサスが得られず、霧散した。スナップディールはその取引に応じなかったことは生着だったとしてそれ以降を「スナップディール2.0」と呼んでいる。2.0において、同社はまたたく間に黒字化し、持続可能な会社になった。フリップカートもまた合併破談以降、ソフトバンクなどの既存投資家がエグジットし、フリップカートの子会社となり、精細を取り戻した。同社は来年以降450億ドルから500億ドルの企業価値での上場を目論んでいる。
グラブとゴジェックの合併協議もまた同じ道をたどるのだろうか。大きな違いはふたつある。ひとつは両者がインドのような一つの巨大な経済ブロックではなく、東南アジアという細やかなグラデーションを持つ市場を相手にしている点だ。もうひとつは、電子商取引という有効性が十分に確認されたものではなく、ギグ・エコノミーという旬が過ぎたビジネスを営んでいることである。
ハードランディング(硬着陸)以外の終着点は失われつつあるだろう。