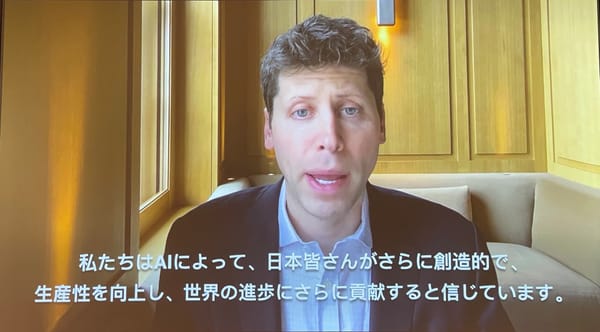中国が隣国と友好的になるべき理由[英エコノミスト]
![中国が隣国と友好的になるべき理由[英エコノミスト]](/content/images/size/w1200/2023/07/393616954.jpg)

中国ほど多くの隣国を持つ国はない。その隣国は混雑しているだけでなく、騒々しい。北朝鮮のようなならず者国家、ミャンマーのような戦争で荒廃した国、インドのような領土紛争が膿んでいる国、日本のような海洋権益を主張する国、そして台湾のような常に侵略を予告している国。どのような状況であれ、中国とうまくやっていくのは難しいが、中国の外交の欠陥はその仕事をさらに難しくしている。
何世紀もの間、中国の指導者たちは、世界を龍の玉座から発する一連の同心円として考えていた。内側の円は皇帝直轄の領土を表していた。そして、日本、ベトナム、朝鮮などの近隣の王国が、朝貢することで皇帝の最終的な権威を認めていた。最も外側に位置するのは外国で、中国との貿易もしばしば朝貢とみなされた。
現在の中国の権力者である習近平国家主席は、この世界観を21世紀風にアレンジしている。国内では自らを共産党の「核心」とし、特に国境地帯では異論を粉砕してきた。世界的には、彼は中国をより主張の強い国にしてきた。しかし、「人々の心を温め、親近感、カリスマ性、影響力を高める」ために中国の近隣諸国をより密接に結びつけようとする彼の努力は、2013年に彼が当局者に指示したように、計画通りには進んでいない。
いくつかの近隣諸国は現在、中国の自己主張の高まりに対抗するため、米国との連携を強めている。中国と最も友好的な国々のほとんどは不安定である。また、中国の意図を恐れている国もある。国連での最近の投票では、中国の近隣諸国の半数がロシアのウクライナ侵攻を非難するために中国に同調しなかった。新疆ウイグル自治区での中国政策への批判を拒否する最近の声明を支持したのはわずか5カ国だった。これらはすべて、習近平の野心を損ないかねない中国外交の弱点を物語っている。端的に言えば、中国が自国の近隣諸国を味方につけることができなければ、本当に世界における米国のリーダーシップに挑戦することができるのだろうか?
強国はしばしば、経済的、軍事的、政治的、文化的に地域を支配することで、自国の繁栄と安全を高めようとする。近代において、フランス、ドイツ、日本、ロシアは、いずれも武力によって地域の覇権を求め、壊滅的な結果をもたらした。欧州連合(EU)は平和的に拡大してきたが、国防と安全保障の面ではいまだ限界にある。唯一、米国だけが長い間、その地域を支配してきた。
それは、他の大国を寄せ付けないようにしている地理的な要因もある。しかし、メキシコやカナダとの自由貿易協定、両国との緊密な防衛関係(特にカナダ)、比較的開放的な国境など、互恵的な取り決めを通じて近隣諸国と結びついてきたことも事実である。米国のソフトパワーも役立っている。
中国の近隣地域ははるかに困難である。中国には2万2,800キロメートルの陸上国境があり、これは他のどの国よりも多い。さらに、8つある海洋国境のすべてが係争中である。そして中国の近隣諸国には、インドやロシアといった経済的・軍事的大国が含まれ、それぞれが地域的野心を抱いている。
隣接する国々は現在、大まかに3つの陣営に分かれている(地図参照)。脆弱または破綻国家(アフガニスタン、ラオス、ミャンマー、ネパール、北朝鮮、パキスタン)、緊密な関係を持ちながらも中国の支配を恐れる敵対国(モンゴル、ロシア、中央アジア諸国)、米国と防衛条約を結んでいるか軍事的に協力している国(インド、日本、フィリピン、韓国、ベトナム、台湾(中国は台湾を国とはみなしていない))である。

中国当局は、地域の覇権を求めることを否定している。彼らの言い分では、中国が望んでいるのは正当な国境を取り戻すことだけであり、国境を拡大したり近隣諸国を支配したりすることではない。彼らは、中国の野心を挫いているのは米国だと非難する。「米国を筆頭とする西側諸国は、われわれに対して全面的な封じ込め、包囲、弾圧を行っている」と習近平は3月の演説で不満を述べた。
ホワイトハウスは最近、中国近隣諸国との関係改善に力を入れている。しかし、習近平が近隣諸国と抱えている問題の多くは、彼らが(バラク・オバマ大統領の時代に)米国から無視されていると感じていたか、(ドナルド・トランプ大統領の時代に)米国から警戒されていたと感じていた時代にさかのぼる。近隣諸国の政府高官や学者によれば、中国に対する懸念はむしろ中国自身の誤った行動から生じている。特に、領土問題での過剰な強硬姿勢、行き当たりばったりで強圧的な経済政策、中国の帝国時代の過去や未来についての大いなる思い込みに根ざした強引な外交アプローチなどが挙げられる。特にロシアのウクライナ侵攻を支持し、「力こそ正義」を暗に示していることを考えると、中国の主張する「安心感」に納得できない人が多い。
1979年のベトナムとの戦争で決着がつかなかった後の30年間、中国は領土問題に関して融和的なアプローチをとり、経済改革に注力しながら安定を選んだ。1991年から2002年の間に、カザフスタン、キルギス、ラオス、タジキスタン、ベトナムとの国境に関する意見の相違を解決した。最も注目すべきは、2008年、19世紀に中国から併合されたウクライナと同規模の領土に対するロシアの支配を強化する一連の協定の最後のものに調印したことだろう。
対立への傾斜は習近平が政権に就く前から始まっていたが、それ以来、領土問題を「民族の若返り」という公約の中心に据え、そのアプローチを強調している。中国は間違いなく、短期的には領土の現状を自国に有利なように変えることに成功している。中国は現在、東シナ海で日本と領有権が重なる岩礁の周辺を船舶や航空機で定期的にパトロールしている。南シナ海の係争中の岩礁に建設された7つの要塞化された人工島は、そこでの領有権を行使する能力を高めている。いくつかの国境紛争地域では、インド軍はもはやパトロールしていない。
しかし、こうした利益は、中国の近隣諸国を警戒させるという代償を伴っている。日本は12月に新たな安全保障戦略を採択し、2027年までに防衛費を倍増させ、新たな反撃能力を持つことを約束した。日本はまた、台湾を含む米国との防衛協力をより緊密にし、米国の同盟国や中国の近隣諸国との安全保障協力を強化している。
南シナ海に対する習近平のアプローチは、中国と領有権が重なる5カ国の中で唯一の正式な米国の同盟国であるフィリピンにも劇的な方向転換をもたらした。前大統領のロドリゴ・ドゥテルテは2016年、米国からの「分離」を宣言し、中国の「イデオロギーの流れ」に沿うことを約束した。しかし、中国がフィリピンの船舶に嫌がらせを続け、約束したインフラ整備を怠ったため、関係は悪化した。
フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は現在、米国との関係を再び強調している。2月には、フィリピン北部にある3つの軍事基地を含む4つの新しい軍事基地へのアクセスをフィリピンに与えた。4月には、1万2,000人の米国軍が参加する過去最大の合同軍事演習が行われた。両者は南シナ海での海軍の共同パトロールの再開を計画している。一方中国は、フィリピンが「地政学的抗争の奈落の底に落ちている」と警告している。
ベトナムも南シナ海で領有権を主張しており、2010年代には中国と何度か海上で対立した。ベトナムもまた、軍事的に米国に接近している。2018年、ベトナムは40年以上ぶりに米国の空母を自国の港に寄港させた。その後、今年6月を含む2隻が寄港している。米国はまた、航空機、無人機、沿岸警備隊用カッター(警備艦)などの防衛設備をベトナムに供給している。
インドもまた、過去4年間にヒマラヤ国境で中国と衝突し、少なくとも20人のインド軍兵士と4人の中国軍兵士が死亡したことを受けて、関係を見直そうとしている隣国である。このような小競り合いは、1962年に中国が短期間の国境戦争に勝利して以来、最も死者が多いものだった。二国間貿易は成長を続けているが(昨年は8.6%増)、インドは中国からの投資を制限し、数十の中国製アプリを禁止し、いくつかの中国企業に税務調査を開始した。
インドはまた、米国やその同盟国とも、二国間でも、米国、日本、オーストラリアを含むクアッドの一員としても、防衛に関してより緊密に協力している。6月にワシントンを公式訪問したナレンドラ・モディ首相は、防衛産業に関する一連の取引に署名した。
中国を苛立たせる隣国同士も、より緊密な協力関係を築いている。インドはベトナムの潜水艦乗員を訓練し、12隻の高速巡視船をベトナムに提供し、ミサイル・コルベットを供与することで合意した。また、インドは最近フィリピンに巡航ミサイルを売却した。日本はベトナムに哨戒艇を、フィリピンにはレーダーを提供しており、フィリピンは2020年以降、韓国から3隻の海軍艦艇を受け取っている。
経済的な側面はそれほど明確ではない。中国は、領有権の主張が対立している国々を含むすべての近隣諸国にとって不可欠なパートナーである。2022年の20カ国との二国間貿易額は20兆ドル強で、過去10年間で74%増加した。これは、米国と欧州連合(EU)の同国との貿易額の合計よりも多い。貧しい国々にとって、中国は大きな投資源でもある。2022年に発効し、中国と近隣8カ国が参加する地域包括的経済連携と呼ばれる貿易協定は、国境を越えた貿易をさらに促進するだろう。
しかし、中国との貿易は偏っており、中国は近隣諸国から買うよりも近隣諸国に売る方が多い。その一方で、近隣諸国は米国と欧州連合(EU)への販売額が中国への販売額を上回っている(図表参照)。さらに、中国はその経済力を使って、自国を怒らせた隣国を罰するという不穏な習慣がある。これも習近平から始まったことではない。2010年、東シナ海での衝突の後、中国は日本へのレアアース鉱物の輸出を禁止した。習近平は就任後、このやり方を拡大した。

モンゴルは習近平の最初の標的のひとつだった。2016年にダライ・ラマの訪問を受け入れた後、中国は融資と通関を保留した。モンゴルはそれ以来、対中貿易への依存度をさらに高めており、輸出品(主に石炭)の約84%を中国が購入している。しかし、モンゴル政府はnatoとのパートナーシップによってヘッジしている。natoは、サイバー防衛の構築、英語による将校の訓練、nato軍(モンゴル軍はコソボとアフガニスタンで活動している)とのより効果的な連携を支援している。
ダライ・ラマをめぐる対立は、内モンゴル自治区における同族の扱いに憤慨する人々が多いこの国で、反中感情を強めることにもなった。内モンゴルでのモンゴル語教育禁止は特に不評だ。モンゴルの元大統領であるツァキアギーン・エルベグドルジは、これを「独立した民族としてのモンゴル人を解体し、排除しようとする残虐行為」と呼んでいる。
しかし、中国による不見識な牽制の例として際立っているのは韓国である。2013年に朴槿恵が大統領に就任した後、彼女は中国との緊密な関係を求め、北京での軍事パレードにも出席した。しかし2017年、韓国が米国に対ミサイル砲台の配備を許可した後、中国は経済ボイコットを行った。それまでは、韓国の牙山研究所が定期的に行っている他国に対する評価調査では、中国は常に10点満点中5点以上だった。昨年は2.7点だった。
韓国は現在、米国との同盟関係を強化し、かつての植民地支配者であった日本との長年にわたる意見の相違を脇に置いている。両者はまた、サプライチェーンにおける中国の役割を減らすという米国主導の努力にも加わっている。その結果、中国周辺国の企業にも新たなチャンスが生まれつつある。韓国の自動車メーカー、現代自動車は5月、今後10年間で25億ドルをインドに投資すると発表した。またベトナム(韓国はすでに最大の外国投資国)は12月、韓国の電子機器メーカーであるサムスンとLGの2社が、さらに60億ドルを投資すると発表した。
より貧しい近隣諸国では、中国の「一帯一路」プロジェクトがその強圧的な傾向を補うのに役立っている。成功例としては、中央アジアを横断する貨物鉄道リンクがあり、現在では中国とヨーロッパの貿易の8%を担っている。中国からラオスへの新しい鉄道は4月に旅客サービスを開始し、世界銀行によればラオスのGDPを21%押し上げる可能性がある。
しかし、このようなイニシアティブは、過剰な約束と地元の感情を無視する傾向によって、しばしば損なわれている。ネパールでは、中国は約束した「一帯一路」プロジェクトのいずれも完了していない。マレーシアは、コストが水増しされているとして、いくつかのプロジェクトを中止した。一帯一路に関連する債務問題は、パキスタンとラオスを債務不履行の瀬戸際に追いやった。また、ミャンマーの内戦はいくつかの大きな中国プロジェクトを遅らせ、広く嫌われている軍事政権を支援する中国に対する国民の支持をさらに低下させている。
中国はまた、怪しげな中国企業や犯罪組織が「一帯一路」におんぶにだっこするのを止められなかった。ラオス、ミャンマー、フィリピンはいずれも、ギャンブル事業に中国人の資金と労働者が大量に流入し、犯罪の増加につながった。これらの国や他の貧しい隣国は、いまだに開発援助を切望している。しかし、中国が経済減速に直面し、「一帯一路」の規模を縮小するなか、多くの国々は、援助が手荷物にならない日本に注目している。
シンガポールのiseas-Yusof Ishak Instituteが最近行った調査では、東南アジアの近隣諸国における中国への不信感が示された。マレーシア、ミャンマー、ベトナム、フィリピンでは、中国への信頼よりも不信感を示す人が多かった。中国の近隣諸国6カ国すべてで日本の方が信頼されており、5カ国では米国の方が信頼されていた。また、中国は米国、オーストラリア、欧州連合(EU)よりも「訪問したい国」「留学したい国」の順位が低かった。
中国との結びつきが強いカザフスタンでさえ、人々は警戒心を抱いている。国境をまたぐ5平方キロメートルの免税ゾーンがある国境交差点、ホルゴスでは、その緊張感が際立っている。草原から蜃気楼のようにそびえ立つ中国側には、レザージャケットから薄型テレビまで何でも揃う2ダースの高層モールがある。盾と警棒を持った中国の機動隊員が目を光らせ、カザフスタンの買い物客でごった返している。一方、カザフスタン側には中途半端な低層モールが2、3軒あるだけで、客は少なく、従業員のほとんどは中国人である。
22歳のカザフ人法学生カナト・アギバエフは、中国側で買ったばかりの安い冬服とリュックサックが気に入っている。しかし、中国の対カザフスタン投資や最近のビザ免除協定について尋ねると、彼は他のインタビューに答えた: "中国に飲み込まれる "とね ロシアのプロパガンダはこのような中国恐怖症を煽る。カザフ族を含む100万人もの中国系イスラム教徒を再教育キャンプに収容している。2022年に中央アジア・バロメーターが行った調査では、エネルギーやインフラプロジェクトへの中国の関与を支持するカザフ人はわずか35%で、2018年のほぼ半数から減少した。
そして、中国の「狼戦士」外交官の胸を張る宣言がある。4月だけでも、マニラの中国大使は台湾のフィリピン人労働者を脅し、パリの大使は旧ソビエト諸国の正当性に疑問を呈した。その1カ月後、習近平は中央アジアの5人の指導者を招き、中国が中央アジアの大部分を支配していた唐の時代のイメージを盛り込んだサミットを開いた。
「まるで皇帝が部族の族長を迎えているようだった」と、サミットで署名された中国とカザフスタン間のビザなし渡航を認める協定に反対する抗議行動を計画したために拘束されたカザフスタンの活動家、ベクザット・マクストゥリーは言う。カザフの政府関係者は、彼の訴えを「不合理」だと一蹴する。政府の数字によれば、カザフスタンで働く中国人はわずか3,412人である。そして、このビザ協定は中国人観光客と同様にカザフスタンのローリー運転手やビジネスマンにも利益をもたらす。カザフスタンの未来は、ロシアや中国に従属することではなく、米国、日本、EU(カザフスタン最大の貿易相手国であり、外国投資家でもある)、そしてカザフスタンで兵器を共同生産しているnatoのメンバーであるトルコなど、多くの大国との緊密な関係にある。
いずれも、中国の近隣諸国が中国に背を向けているという意味ではない。その経済力を考えれば、そんなことは考えられない。しかし、習近平氏の覇権主義的野望が挫折し、国境を接するより安定的でダイナミックな国々が習近平氏のイニシアチブに抵抗するか、あるいはヘッジをかける一方で、最も不安定で見通しの立たない国々が中国の支援への依存を強めていくという未来を示唆している。米国とその同盟国にとっての課題は、中国の近隣諸国にこれまで以上にヘッジする方法を提供することである。習近平にとって、問題はより本質的なものである。中国は近隣諸国との関係において、自国が卓越した存在でないことを受け入れることができるのだろうか?■
From "Why China should be friendlier" to its neighbours, published under licence. The original content, in English, can be found on https://www.economist.com/briefing/2023/07/04/why-china-should-be-friendlier-to-its-neighbours
©2023 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
翻訳:吉田拓史、株式会社アクシオンテクノロジーズ