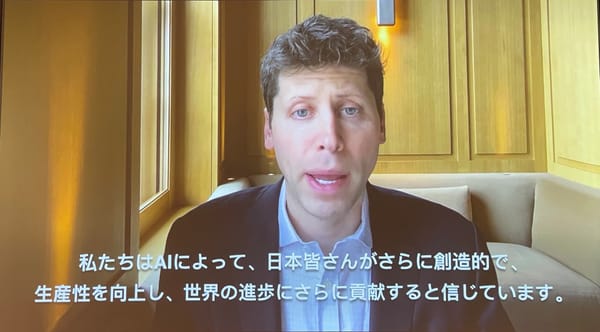東アジアの新しい家族像 政府は現実に追いつくのに苦慮[英エコノミスト]
![東アジアの新しい家族像 政府は現実に追いつくのに苦慮[英エコノミスト]](/content/images/size/w1200/2023/07/getty-images-JrS2WNGiuUY-unsplash.jpg)

彼女は卵子を凍結することで、将来子どもを持つ能力を維持することを望んだ。しかし、彼女が訪れた北京の病院の医師は、中国の法律では結婚している夫婦にしかできないとして、彼女の要求を拒否した。それどころか、もっと早く結婚して妊娠するよう勧めた。それでもめげずに、彼女は2019年、女性差別と権利侵害で病院を訴えた。2022年、裁判所は病院を支持する判決を下したが、シューさんは控訴した。
彼女は、シングルマザーに対する否定的なステレオタイプにつながると見ている中国の規制の変更にまだ希望を抱いている。「シングルマザーで子どもを持ちたいと願う女性たちの、より正真正銘の、より多様な姿をみんなに見てほしいです」と彼女は言う。彼女のケースは、20代後半から30代前半の女性を中心に、ソーシャルメディア上の何万人ものフォロワーからの支持を集め、議論の的だ。「この政策を更新できないからといって、全世代の独身女性の要求をないがしろにしなければならないのでしょうか?」
シューさんの経験は、東アジア全域で起きているより広範な傾向を示している。彼女の両親の世代では、中国、日本、韓国、台湾の家庭は、男性が働き、女性が家庭を守るという、儒教的価値観を広く共有する単一民族の子持ち夫婦が中心だった。伝統的な家族は依然として広く残っているが、この地域全体の家族ははるかに多様化している。このプロセスが最も早く始まった日本では、1980年には少なくとも1人の子どもがいる夫婦が世帯の42%を占め、単身世帯はわずか20%であったが、2020年には子どもがいる夫婦が世帯の25%に減少し、単身世帯が38%を占めるようになった。ハーバード大学の社会学者であるポール・チャンは、今日の東アジアでは「世帯構造の多様化こそがストーリーだ」と言う。
しかし、東アジアの多くでは、結婚や家族をめぐる法律や社会的モラルが新しい現実に遅れをとっている。政府はそれらを改正・改革する代わりに、伝統的な家族を復活させようと、結婚や出産に金銭的なインセンティブを与えることで対応してきた。核家族は、人口減少を逆転させようとしている東アジアにとって失敗だった。答えは、法的、社会的、文化的な独占を強化することではなく、他の環境で子どもを育てることを難しくしている障害を取り除くことである。ここに紹介する4組の画期的な家族が示すように、すでに多くの人々がそうしようとしている。
家族のあり方は、この地域の人口動態、ひいては経済力に大きな影響を与える。国連によれば、東アジア4地域の人口は2020年から2075年の間に合計で28%減少するという。国連によれば、東アジア4地域の人口は2020年から2075年の間に合計で28%減少すると予測されている。同じ期間、世界のGDPに占める東アジア4地域の割合は26.7%から17.4%に低下するとゴールドマン・サックスは予測している。
それならば、政治指導者たちが家族を喫緊の優先政策と考えても不思議ではない。中国の習近平国家主席は「出生率を高めるための国策システム」を約束し、「新時代の結婚文化」を推進するための国家的取り組みを開始した。岸田文雄首相によれば、日本は少子化で「社会として機能し続けられるかどうかの瀬戸際」に立たされており、政府は4月に「こども家庭庁」を発足させた。韓国の尹錫烈(ユン・ソクヨル)大統領は3月、この課題に焦点を当てた政府の新組織の設立総会で、自国の出生率を「緊急の考え方」が必要な「重要な国家的課題」と呼んだ。台湾の蔡英文総統は、少子化を「国家安全保障問題」と呼び、すべての人が「結婚する意欲を持ち、子どもを持つ勇気を持ち、老人を介護する喜びを持つ」ようにするための政府支援を約束した。
世界の多くの地域と同様、20世紀の東アジアでも工業化と都市化が進み、多世代にわたる大家族から核家族へとシフトした。同時に、政府は家族計画政策を推し進めたが、それは皮肉なことに、今日の視点から見れば、生まれる子どもの数を減らそうとするものだった。たとえば韓国では、1970年代にパイプカット手術を受けた男性は、住宅抽選で優遇されたり、兵役訓練を免除されたりした。中国は、1980年から2016年まで断続的に実施された悪名高い一人っ子政策によって、人為的に出生率を抑制した(中国は2016年に一人っ子政策を二人っ子政策に切り替え、2021年には三人っ子政策に切り替えた)。
平均世帯人員は数十年にわたり、この地域全体で減少している。台湾では、2001年には核家族が世帯の47%を占め、単身世帯と子どものいない世帯は24%に過ぎなかったが、2021年には単身世帯と子どものいない世帯の割合は34%に上昇し、核家族は33%に減少した。韓国では1980年には単身世帯が4.8%を占めていたが、2021年には単身世帯が33.4%を占め、歴史的な高水準となる。中国では、2000年には8.3%の世帯が単身世帯であったが、2020年には25.4%に増加する。
晩婚化、あるいは結婚を完全にスキップする若者が地域全体でますます増えている。中国は2022年に680万組の婚姻届を提出したが、これは1985年にデータが入手可能になって以来最低の数字であり、ピークだった2013年の1,350万組の約半分である。韓国の同年婚姻件数は19万2,000件で、データ収集が始まった1970年以降で最低となった。台湾の新婚件数は12万5,000組で、ピークの2000年から30%減少した。日本では50万4,878組が結婚し、前年よりわずかに増加したが、それでも第二次世界大戦後最低の水準である。
子どもも産まないと決めた人が多い。かつては必要不可欠と考えられていた子どもは、今やオプションと化している。日本の出生率(女性が生涯に産むと予想される子どもの数)は1970年代後半から低下し始め、2022年には1.26と過去最低を記録した。中国でも昨年、出生率が1.2を下回り、1961年以来初めて人口が減少した。それでも、2022年に出生率の世界最低記録を樹立した韓国(0.78)や台湾(0.87)を上回っている。台湾では昨年、新たに登録されたペットの数(23万匹)が、生まれた子どもの数(14万匹)を上回った。台湾人の中には、自分たちのペットを「毛皮を着た子ども」と呼ぶ人もいる。
日本の社会学者である西野理子(東洋大学教授)は、「家族の同質性という考え方が揺らいでいる」と言う。かつてこの地域の多くでタブーとされていた結婚前の同棲も、今では受け入れられるようになった。ゲイやひとり親は、家族を作り子どもを持つ法的権利を求めている。共働き世帯が一般的になり、離婚や再婚も増えている。高齢化も家族のあり方を変えている。65歳以上の高齢者が人口の30%近くを占める日本では、新しい言葉が生まれた。 「8050(はちまる・ごうまる)」「9060」家族とは、高齢の親と中年の子どもが同居する家族のことである。
台湾は、誰が正式に家族とみなされるかを再定義することに最も力を入れている。2019年に同性婚を合法化し、今年5月には同性カップルの養子縁組を合法化した。近年は移民の統合も進め、多文化を含む台湾の家族を再定義している。2022年には、主に中国や東南アジアからの結婚移民が57万7,900人となり、台湾の総人口の約2.5%を占めた。
台湾北西部の都市、桃園で育ったツォウ・チアチンさんは、父親が台湾人、母親がフィリピン人だが、テレビのレポーターが外国人花嫁が逃げ出す可能性や、彼女たちにお金やパスポートを渡すことの危険性を論じているのをよく目にした。現在26歳のツォウさんによれば、彼女たちはまるで「人間ではなく、物」であるかのように話していたという。学校ではフィリピン人家族のことは話さなかった。近所の人たちや親戚でさえ、彼女の母親をいじめた。
最近、台湾の蔡総統は、台湾を中国と区別するための政治的な動きとして、多文化主義を推進し始めた。ツォウさんは、東南アジアの文化を祝うイベントに招かれ、頻繁に講演している。彼女は政府の新移民のための委員会の委員を依頼された。2020年、彼女は両親とともにフィリピン料理レストランをオープンし、フィリピンについての質問が過去の「外国人の花嫁」というステレオタイプに集中しなくなった台湾人客を惹きつけた。ツォウさんの10歳年下の弟は、彼女が学校で直面した差別を経験していない。「クラスメートに両親の国籍が違う人がたくさんいるのは普通のことではないですか?」 ツォウさんがフィリピン人とのハーフであることはどんな感じか尋ねると、彼は肩をすくめた。 彼の何気ない態度は、台湾がいかに遠くまで到達したかを示している、と彼女は言う。
この傾向は、1970年代以降、豊かな欧米諸国を席巻した「第二次人口移行」と呼ばれる現象に似ている面もある。しかし、東アジアでは異なる力が働いている、とハーバード大学のチャンは主張する。「この変化は、個人の勝利ではなく、不安、社会問題、社会的葛藤によって引き起こされている」。主に豊かな国々からなるOECDでは、婚外子の割合が40%を超えているが、日本、韓国、台湾では5%以下である(中国は公式データを取っておらず、婚外子の登録や手当の受給が困難である)。このように、東アジア全体の出生率の低下は、結婚の減少によるところが大きい。例えば日本では、既婚女性の出生率は2022年には1.9となり、1971年の2.2からわずかに低下しただけである。
東アジアで伝統的な家族が減少している大きな理由のひとつは、経済的な不安定さである。アンケート調査では、多くの人がまだ結婚したいと答え、子どもも何人も産んでいる。しかし、そうする余裕がないと感じる人が増えている。高い教育費と住宅費が、子どもを持つことを贅沢なものにしている。多くの男性、特に不安定な仕事に就いている男性は、結婚生活をうまくいかせるだけの十分な収入が得られないことを恐れている。ハーバード大学のメアリー・ブリントンは、「結婚と家族は、余裕があって初めて実現できるものになりつつある」と言う。
しかし、お金はせいぜい物語の一部でしかない。制度や文化の硬直性も、若者が新しい家族を築くことを難しくしている。プリンストン大学のジェームズ・レイモは、東アジアにおける結婚と出産のパターンの変化は、急速な社会的・経済的変化と、結婚と家族関係の不変の構造との間の緊張から生じている、と主張する。
女性の教育水準が上がったとはいえ、伝統的な性別役割分担はいまだに家庭内に浸透しており、掃除、料理、育児、高齢者の介護といった「女性らしい仕事」はすべて女性が行うことが期待されている。東アジアでは育児休暇を取得する男性が増えているとはいえ、まだ少数派である。長時間労働と融通の利かない企業文化は、仕事と家庭の両立を世界の他の地域よりもさらに難しくしており、多くの女性にとって結婚の機会費用を引き上げている。「そのため、多くの女性が結婚を完全に拒否することに決めているのです」と台湾の研究機関アカデミアシニカの社会学者、アリス・チェンは言う。カリフォルニア大学アーバイン校の人口学者ワン・フェンは、これを東アジアの「静かなジェンダー革命」と呼んでいる。
反動は韓国で最も顕著になり、「ジェンダー戦争」と呼ぶ論者もいる。2018年の夏、#MeToo運動に触発され、何千人もの女性がいわゆる「モルカ」ビデオ、つまり公衆トイレ、更衣室、オフィス、靴などに隠された盗撮カメラに抗議するために街頭に繰り出した。その結果、女性たちに髪を切り、化粧を捨てることを奨励する「脱コルセット運動」が生まれた。女性たちはまた、結婚しないことを誓い、自らを「비혼(ビホン、進んで結婚しない)」と宣言するようになった。
イ・ミンギョンはいつも家族を養いたいと思っていた。現在30歳の作家であり活動家であるイ・ミンギョンさんは、小学生の頃、将来の夢を尋ねられた。彼女は「一家の大黒柱」と答えた。しかし、家父長制の韓国で若い女性として、それは不可能に思えた。「男性と一緒に暮らしているのに、どうして稼ぎ頭になれるの?」
2020年にレズビアンであることをカミングアウトした後、イさんは別の種類の家庭を築くことを決意した。韓国では同性婚は依然として違法であるため、彼女はゲリラという会社を設立した。この企業は、女性に語学、文章、財政を教える学校、女性のためにスペースを貸す不動産業、女性アーティストのためのタレントマネジメント会社、そして女性のためのシェルターで構成されている。「ゲリラの目的とは、女性を守り、教育し、投資することで、家父長制と戦うのです」とリーさんは宣言する。
ゲリラはその後、リーさんのパートナー、養女(リーさんよりわずか2歳年下)、もう一組の夫婦、友人、そして犬を含む7人家族に成長した。「血の繋がりはなくても、知的な繋がりだけで家族になれるということを世界に示したかったのです」とリーさんは言う。
政策立案者たちは、現代の若者たちがもっと結婚し、子孫を残すことを望んでいる。しかし、それを奨励するための彼らのアイデアは、ほとんどが経済的なインセンティブで構成されている。台湾政府は出産に補助金や賞金を出している。中国は32の「国家結婚習慣改革実験区」を設置し、婚姻届の迅速化、結婚相談、費用を抑えた集団結婚式などを実施している。韓国の尹大統領は3月、人口減少を食い止めるために過去16年間に費やされた2億8,000億ウォン(約2,150億円)はほとんど効果がなかったと認めた。日本では、岸田首相が今後3年間、子ども・家族支援策に年間3.5兆円を追加支出すると約束した。
同時に、多くの(男性)指導者も伝統主義を強化している。習近平は、中国の「民族の若返り」への道のりの一部として、伝統的な男女の役割を支持する儒教の復活を推進している。共産党はフェミニストやLGBTのグループを検閲し、最も著名な活動家を逮捕した。地元の役人たちは、親孝行や家族の大切さについて講義を行っている。
尹大統領の進歩的な前任者である文在寅氏の下で、男女平等家族省は社会的給付を受けることができる「家族」の定義を、結婚している異性カップルだけでなく、未婚のカップル、片親、さらには同性カップルまで拡大した。尹氏はこれらの措置を撤回し、同省を完全に廃止すると宣言した。ソウルにある延世大学のイ・ドフンは、韓国政府の政策はいまだに男性中心だと言う。「子どもを産み育てることは、完全に女性の責任ではないということを示す政策が必要だ」。尹氏は代わりに、韓国の出生率の低さをフェミニズムのせいにしている。
日本の家族法は時代遅れだ。結婚した夫婦は別姓を名乗ることができないが、与党の自民党はこの慣習を変えようとしない。小倉将信・こども政策担当相は、他の男性議員2人とともに、重りのついたジャケットを着て1日妊娠を疑似体験するというパフォーマンスでよく知られている。多くの自治体が同性カップルに象徴的な「パートナーシップ」証明書を発行しているが、国は同性婚の合法化に難色を示している。その代わり、自民党は今月、結婚の権利には一切触れず、同性愛者を「不当な差別」から歯がゆく保護する法案を不承不承可決した。
これでは、東京近郊の千葉に住む五十嵐隼人と菅野孝文のようなカップルには、ほとんど助けにならないだろう。ふたりは出会い系アプリで知り合い、地元のパートナーシップ・システムを通じて婚姻届を提出した。精子や卵子の提供は制限されており、ゲイカップルが里子を迎えることはしばしば禁じられている。
これらの制限を回避するために、2人は非常に変わった解決策を思いついた。同じく子どもを持ちたがっているレズビアンのカップルを見つけたのだ。二組は一緒に二人の子どもを作り、一人目は女性が、二人目は男性が育てることに合意した。五十嵐さんと菅野さん(下の写真)は最近赤ちゃんを迎え、家族のテーマであるリトル・マーメイドにちなんで、海の字を含む「ななみ」と名付けた。親権を確保するための法的枠組みはなく、まず母親が親権を放棄しなければならない。五十嵐さんはシングルファーザーとして養子縁組をし、菅野さんも次男として養子縁組をする。「政治家は家族の形がひとつしかないと思っている」と五十嵐さんは嘆く。
多くの点で、世論は政治指導者たちよりも進んでいる。世論調査によれば、自民党の有権者の過半数を含む日本人の過半数が、同性婚の合法化と夫婦別姓の容認の両方を支持している。日本の飲料会社サントリーの社長であり、日本経営者協会の新会長に就任した新浪剛史は、「カップルの人生についての多様な考え方」に対する理解を深めるよう呼びかけている。また、中国の中央当局は伝統的な男女の役割分担への回帰を推進しているが、若い世代は男女の役割分担に寛容になり、男女平等を声高に主張するようになっている。昨年、人身売買された花嫁が農村の男性の小屋で首を鎖でつながれた状態で発見された事件や、レストランで誘いを断った女性を男性が殴打する事件がビデオに収められた。
硬直的な家族構成に固執することは、人口逼迫を激化させ、同時に人々が幸せで自由な生活を送る能力を制約することになる。より賢明な政策は、変化する現代家族の現実をよりよく反映させようとするものだ。東京大学の白波瀬佐和子教授は、「もっと柔軟な家族形態が必要です」と言う。「構造を硬直的に設計すると、劣化してしまうのです」。特に、新しい仕組みは、東アジアの公私両面の生活をいまだに形作っている家父長制的な社会風土と、高学歴で権力を持つ女性との間で高まっている緊張関係に取り組まなければならない。それが実現するまで、女性たちは妻や母親という伝統的な役割に抗い続け、場合によっては家族のあり方を再定義し続けるだろう。
From "East Asia’s new family portrait", published under licence. The original content, in English, can be found on https://www.economist.com/interactive/asia/2023/06/30/east-asias-new-family-portrait
©2023 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
翻訳:吉田拓史、株式会社アクシオンテクノロジーズ