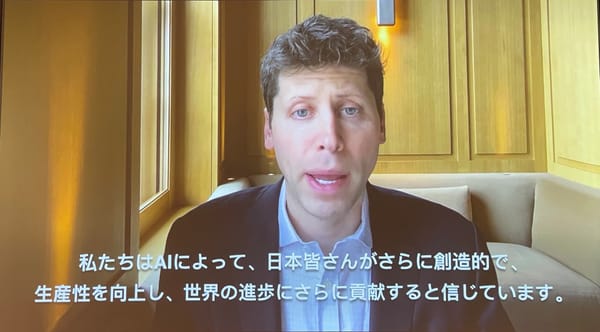「反労働」が米掲示板サイトで大人気
サブレディット「r/antiwork」(アンチワーク、反労働)は、170万人の自称「怠け者」たちが集うコミュニティで、仕事を辞めた体験談を投稿したり、資本主義を揶揄するミームを共有したり、企業の独裁者から威圧的な中間管理職まで、あらゆる種類の「ひどい上司」に仕返しすることに喜びを感じている。

サブレディット「r/antiwork」(アンチワーク、反労働)は、170万人の自称「怠け者」たちが集うコミュニティで、仕事を辞めた体験談を投稿したり、資本主義を揶揄するミームを共有したり、企業の独裁者から威圧的な中間管理職まで、あらゆる種類の「ひどい上司」に仕返しすることに喜びを感じている。サブレディットは5ちゃんねるにおける「板」の意だ。
コロナウイルス問題で多くの人が自分のキャリアを見直す中、サブレディットの登録者数は2020年10月の18万人から今月は170万人にまで膨れ上がった。
昨年、アメリカでは膨大な数の人々が仕事を辞めており、米労働統計局のデータによると、11月には450万人もの人々が仕事を辞めました。この数字は、2001年に労働省が調査を開始して以来、最も高い「退職率」である。データによると、多くの労働者がより良い条件のオファーを受けて仕事を辞めたと推定されている。
ゴールドマン・サックスは、11月に発表した調査報告書の中で、反労働運動は労働力人口にとって「長期的なリスク」になると警告しているほどだ。このサブレディットの規模は、ゲームストップの株価暴騰で有名なWallStreetBetsスレッドの10分の1程度だが、Goldmanは、Antiworkが1日あたりのコメント数でWallStreetBetsを上回っていると指摘している。
このフォーラムのスローガンは、"Unemployment for all, not just the rich!”(金持ちだけでなく、すべての人に失業を!)だ。2013年から存在しているが、秋に購読者数が急増し、この3カ月間だけで2倍になった。その背景には、パンデミック時の労働市場の状況に対する不満がある。以前は当たり前だった条件や給与を受け入れない労働者が増えている。
最初は資本主義を弱体化させるための場所として考えられたが、今では多くの人がこのグループを、労働者の権利について議論したり、雇用主に対する不満をぶちまけたり、人々が辞めるときのカタルシスを味わえるスクリーンショットや動画を投稿する場所として利用している。
このサブレディットの人気の高まりは、メディアからの注目も集めている。最近、当初の運営者であったドリーン・フォードが米テレビネットワーク「フォックス・ニュース」の番組に出演したことでコミュニティが混乱し、1月下旬に一時的にサブレディットが非公開になった。
フォードは「反労働運動」の初期のパイオニア。反労働運動とは、従来の仕事をできるだけ減らしたり、完全にやめて自営業にしたりして、余暇を優先させることを奨励する運動だ。しかし、テレビ出演がコミュニティの怒りを買い、現在はグループから削除されている。
よりアナーキーなアプローチをとるメンバーもいるが、多くのメンバーは最低賃金や低賃金の仕事に従事しており、自分の置かれている状況についてアドバイスを求めたり、労働条件の改善を訴えたりする手段としてサブレディットを利用している。
また、設立当初のモデレーターがより過激な反労働者のスタンスをとっているのに対し、改革派は反労働者というよりも親労働組合のスタンスをとっており、コミュニティの性質はだいぶマイルドになりつつあるようだ。