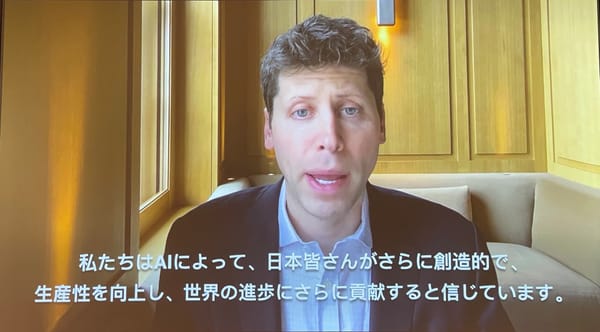予測不能な未曾有の出来事の衝撃 『ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質』
ブラック・スワンは、すべての白鳥は白であるべきだというあなたの信念を突然打ち砕く黒い白鳥であり、あらゆるもののあり方を激変させる極端な出来事の象徴です。タレブの主張は、希少かつ極端な出来事は、金融市場およびより広い世界において、通常想定しているよりもはるかに大きな影響を与えるというものです。

このブログは『ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質』の書評です。ブラック・スワンは、すべての白鳥は白であるべきだというあなたの信念を突然打ち砕く黒い白鳥であり、あらゆるもののあり方を激変させる極端な出来事の象徴です。著者のナシム・ニコラス・タレブの主張は、希少かつ極端な出来事は、金融市場およびより広い世界において、通常想定しているよりもはるかに大きな影響を与えるというものです。
確立分布の代表的な形として「正規分布」を用いることが多いです。確かに、さまざまな現象が正規分布で近似できます。しかし、タレブは金融市場や我々の世界の大半がべき分布に従うものだと主張します。実際、タレブより先に同様の主張をする人はいました。たとえば、本書よりも前に出版された『 歴史は「べき乗則」で動く』(マーク・ブキャナン)は、様々な歴史的出来事に光を当て、そこにべき乗則の存在を見出す非常に面白い読み物です。
この良書に対しお世辞にも読みやすい書籍とは言えない本書が注目を浴びた理由は、世界金融危機のピークとなった2008年夏のリーマン・ショックの1年前に出版されており、現実の出来事が、タレブの説の信憑性を高めたことが大きいでしょう。
タレブは本書の中で、1988年のLTCM(ロングタームキャピタルマネジメント)破綻、2001年の米国同時多発テロ事件、2004年のスマトラ島沖地震、Googleの驚くべき成功など、数々の社会現象をブラック・スワンと位置づけています。他方、一部の経済学者は1987年の株式暴落をプログラム取引のせいにしましました。1929年の暴落は過剰な借金が原因だとし、1997年の暴落はアジア諸国の対外負債の膨張を原因としましたが、カタストロフィが発生するメカニズムをうまく説明できないでいました。
ブラックスワンとは、べき分布のテールで発生する稀で極端な出来事のことを指し、それらが起きた後は物事のあり方が一変してしまう現象を指しています。統計学では通常、正規分布で仮定し、大概の場合、それで近似がとれます。しかし、実際には、正規分布では近似できない現象も多いのです。
べき分布は一種のベルカーブ(正規分布)に似ていますが、そのテールははるかに長いため、極端なイベントがかなり頻繁に発生します。同種のべき分布で発生する大きなイベントをめぐる理論としては、ディディエ・ソネットの「ドラゴンキング」が存在します。こちらは複雑系の手法を応用することで、「予測不可能性を予測しようとする」ものです。
本書はエッセイ形式をとっており非常に困惑を生み出すような文体で、ブラックスワン現象の比喩を重ねていきます。「オーストラリア大陸(の黒い白鳥)が発見されるまで、旧世界の人たちは白鳥と言えばすべて白いものだと信じて疑わなかった」「はじめて黒い白鳥が発見されたとき、一部の鳥類学者(それに,鳥の色がものすごく気になる人たち)は驚き、とても興味を持ったことだろう」「何千年にもわたって何百万羽も白い白鳥を観察して確認してきた当たり前のことが、たった一つの観察結果で完全に覆されてしまった」と説明しています。
タレブは、物理学者マンデルブロの成果に触れています。マンデンブロは、金融市場の価格変動が正規分布ではなく、理論的には分散が無限大である安定分布に従っていると主張しました。マンデンブロはフラクタル幾何学の創造者であり、金融の世界では長らく異端者の扱いを受けましたが、後続者たちの研究が彼の貢献を明らかにしたという経緯があります。タレブは、黒い白鳥がいる世界では、予測をしようとするのではなく、その世界に順応するしかない、と主張しています。そして、反知識を利用して、失うものがほとんどなく、万が一起これば得られるものが大きいものに賭けるのがよいと主張します。すなわち、彼がトレーダーとして採用する「バーベル戦略」を導入する。これは可能な限り超保守的かつ超積極的になることを意味します。お金の一部(85〜90%ぐらい)をものすごく安全な資産(アメリカの国債など)に投資し、残りはものすごく投機的な賭け(オプショ ンなど)に投資する戦略です。
タレブは次の書籍でブラックスワンがいる世界に順応するべきであると考え、反脆弱性(アンチフラジャイル)という考え方を提案します。
ブラック・スワンはあらゆるところで言及される言葉になりました。たとえば、最近では、国際決済銀行(BIS)が、各国・地域の当局が気候変動に伴うリスクに対処しなければ、システミックな金融危機を引き起こす「グリーン・スワン」を招くことになりかねないとする分析論文を公表しています。厳密な科学の言葉ではないものの皆の共通理解を深めるバズワードを作ったことは、タレブの重要な仕事だったでしょう。
タレブはレバノン系アメリカ人のエッセイスト、哲学・数学研究者、オプショントレーダーです。タレブは現在、ニューヨーク州立大学のTandon Engineering リスクエンジニアリング学科の特任教授(4分の1の職位のみ)を務めています。
Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash