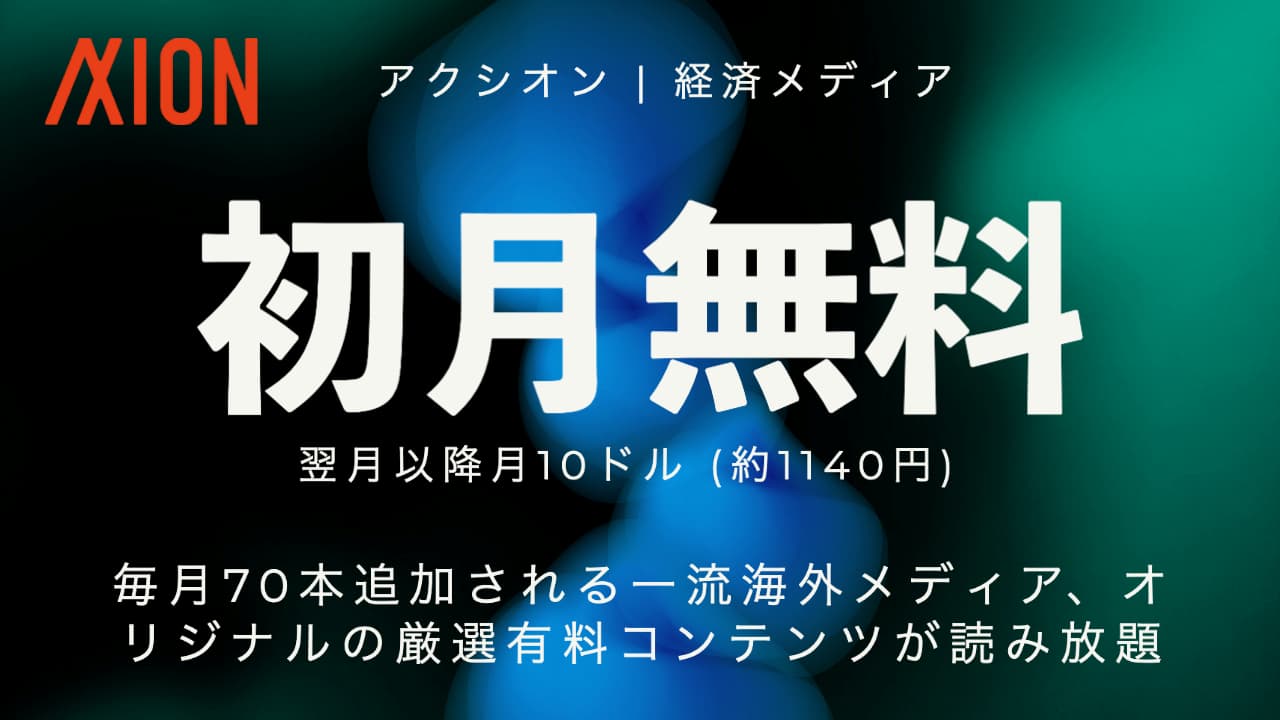『ドライブ・マイ・カー』のオスカー受賞は日本映画の緩やかな復活
『ドライブ・マイ・カー』のアカデミー賞受賞は、日本映画の緩やかな復活をもたらしている。しかし、このインディー映画が海外で人気を博した性質は、閉鎖的な国内の業界での評価を冷え込ませている側面もある。

[著者:リッチ素子]東京 - 前回、日本作品がアカデミー賞国際映画賞を受賞したのは13年前。
結局のところ、日本映画は、黒澤明、溝口健二、小津安二郎といった監督を世界映画の巨人として世界中の批評家や映画人が賞賛していた20世紀半ばの栄光から長い間色あせていた。
今年受賞した『ドライブ・マイ・カー』は、悲しみと芸術と人間のつながりについての静かで破滅的な瞑想で、国際部門で圧倒的な人気を誇り、脚色賞、監督賞、作品賞にもノミネートされた。
濱口竜介監督のアカデミー賞受賞は、日本の映画作家が国際的な評価を得るためにゆっくりと時間をかけて戻ってきたことの、ある意味締めくくりとなるものだ。3年前、是枝裕和監督の『万引き家族』はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した後、アカデミー賞の国際部門にもノミネートされ、黒沢清監督は2020年のヴェネツィア映画祭で『スパイの妻』で監督賞を受賞している。
しかし、ある意味、『ドライブ・マイ・カー』の国際的な成功は、ほとんどの映画が日本国外に出ることがない偏狭な国内映画産業の制約を超越したことに由来している。
村上春樹の短編小説を原作とする濱口監督の映画は、「外国人が受け入れやすく、理解しやすい日本」を描いていると、テレビプロデューサーで元映画評論家の津田環は言う。この映画の内容は、定義上、国際的なものである。主人公が演出するチェーホフの『ワーニャ伯父さん』は、韓国語の手話を含むさまざまな言語を話す多国籍の俳優が出演している。
津田は「誰もが持っているけれども、なかなか口にすることのない感情に触れることができる」と語った。「日本のことを理解していないと好きになれない、理解できない映画だ」。
濱口は、アカデミー賞受賞後のバックステージインタビューで、この映画のテーマは国境を越えてよく翻訳されていると思うと語り、「喪失、そして喪失後の生き方についてのこの物語は、多くの人々の心に響いたと思う」と通訳を介して語った。
国際色豊かな日本を表現し、社会的に孤立して生きる登場人物を描いたこの映画は、日本社会に対する現在の欧米の印象とも呼応しているかもしれない。
イギリスのシェフィールド大学で日本学を教えるジェニファー・コーツは、「私たちは、より広い国際文化が現在日本に対して抱いている日本らしさのビジョンを見ている」と述べた。ニュースメディアが描く孤独の流行や「ひきこもり」と呼ばれる現象など、海外の批評家や観客の心をつかんだ映画は、「静かなトラウマを描いた映画」において「距離を置いたスタイル」を特徴とすると、コーツは述べている。
それでも、2020年に英語作品以外で初めてアカデミー賞作品賞を受賞し、アカデミー史に名を刻んだポン・ジュノ監督による階級闘争を描いた韓国のスリラー『寄生獣』とは異なり、『ドライブ・マイ・カー』は日本社会の問題を正面から取り上げてはいない。その社会的メッセージはより静かで、外国人観光客に国境が閉ざされ、移民問題が何かと騒がれる日本で、内向き志向から脱却するように働きかけているのかもしれない。
日本での興行成績は、8月の公開以来、8億8,900万円にとどまっており、日本での観客のほとんどは、オスカーにノミネートされた後、ようやく獲得したものだ。「日本人が映画館に足を運ぶきっかけになったのは、海外の映画賞のノミネートだった」と津田は語る。
国内での不振は、過去14年間、国産映画がアメリカの大作を上回ってきた日本では特筆すべきことだ。
濱口は、日本の主流である製作システムの中で映画を作ったわけではない。このシステムでは、映画プロデューサー、広告代理店、テレビ局、さらには化粧品会社などが資金を提供し、監督の芸術的独立性をしばしば奪ってしまうのだ。その代わりに彼は、国内市場向けにマーケティング力のない小規模な制作会社に独立した資金を求めた。
「『ドライブ・マイ・カー』が実は日本映画界に対する反論であると主張することは可能だ」と、イェール大学の東アジア文学・映画教授で日本映画を専門とするアーロン・ゲローは言う。「アカデミー賞を受賞したし、日本の映画産業はこれで利益を得るだろう」と言う人もいるかもしれないが、そうではないという議論もある。「なぜなら、これはある意味、日本の映画産業と対立する映画だからだ」
日本の映画ファンは昨年、映画館で約1,620億円(13億ドル)を使い、そのうちの80%近くが日本で作られた映画のチケットによるものだ。しかし、国産映画の多くは国際的な観客を獲得するチャンスがほとんどないと、映画研究者は言う。
南カリフォルニア大学のケリム・ヤサール助教授(東アジア言語文化)は、「日本の映画やテレビの多くは、非常に平凡な演技によって妨げられている」と語る。多くの映画では、テレビのバラエティ番組に出演し、演劇の訓練を受けていない、いわゆるアイドルが起用されており、本格的な俳優というよりは、ソーシャルメディアの「インフルエンサー」に近い存在である。
日本では、濱口の受賞は冷ややかな反応だった。岸田文雄首相の官房長官である松野博一は、毎日の記者会見で祝辞を述べた。しかし、日本最大の新聞のひとつである朝日新聞の 文化くらし報道部で映画や放送を担当する小峰健二は、『ドライブ・マイ・カー』の受賞について、この映画は主要スタジオのバックアップを受けておらず、資金もほとんど得ていなかったため、「非常に恥ずかしい状況」だと表現した。
濱口の恩師である元東京大学総長の蓮實重彦は、短いメールのやりとりの中で、「アカデミー賞には全く興味がない」と述べ、『ドライブ・マイ・カー』は「優れた作品とは言い難い」と詳しい説明もなく書いている。
しかし、テレビプロデューサーである津田は、『ドライブ・マイ・カー』のアカデミー賞での成功は、日本の映画製作者が海外の観客を考慮するきっかけになるかもしれないと語った。
「特に今はストリーミング、ネットフリックス、アマゾンなどの存在により、日本の映画やテレビ番組が世界中に配信され、アクセスしやすくなっている」と津田は言う。「そのため、海外の視聴者がどのような認識を持っているのか、意識する必要があると思う」
一方、濱口は、この映画を制作したとき、より広い範囲の観客のことはあまり考えていなかったという。「私自身は映画を見る人間なので、自分なりの基準を持っている」とアカデミー賞後のバックステージインタビューで語った。「だから、自分自身の個人的な基準について、そして自分のやっている映画製作がその基準を満たしているかどうかを考えている」
Original Article: ‘Drive My Car’ Oscar Is a Slow-Burn Return for Japan’s Cinema. © 2022 The New York Times Company.