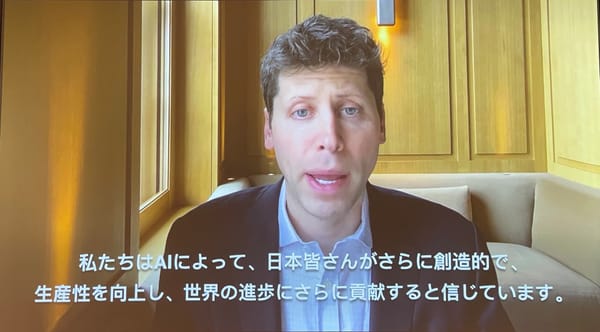日本企業は国際的なサステナビリティの動きへの対応を迫られる
サステナビリティ(持続可能性)への国際的な関心が高まるにつけ、日本企業もその対応を迫られることになる。欧州で進む炭素税、国境炭素税のような税務課題から、ESG投資家による要求への対応など多岐に渡るだろう。

要点
サステナビリティ(持続可能性)への国際的な関心が高まるにつけ、日本企業もその対応を迫られることになる。欧州で進む炭素税、国境炭素税のような税務課題から、ESG投資家による要求への対応など多岐に渡るだろう。
売上規模100億円以上の日本企業に勤める管理職に対して行われた「PwC 地政学リスクサーベイ」(2021年8月実施)で、最も懸念される地政学リスクのひとつとして、日本企業はサステナビリティ/気候変動問題を挙げた。
これは2019年の前回調査にはなかったもので、この間にサステナビリティへの世界的な関心が急激に浮上したことを示唆している。
PwC税理士法人パートナーの白土晴久は、各地域での炭素税や国境炭素税の導入の動きのようなサステナビリティ活動が海外展開する日本企業に影響する可能性に言及した。
温室効果ガス排出削減のための政策ツールの1つとして、炭素税、排出量取引制度などのカーボンプライシングを導入する国・地域が拡大している。カーボンプライシングとは、二酸化炭素(CO2)排出に対して価格付けし、市場メカニズムを通じて排出を抑制する仕組み。炭素税に代表される「価格アプローチ」と、排出量取引制度(ETS、Emission Trading Scheme)に代表される「数量アプローチ」、大きく2通りある。
また、EUが最近導入を決めた国境炭素税は、気候変動対策をとる国が、同対策の不十分な国からの輸入品に対し、水際で炭素課金を行うことを指す。さらに、自国からの輸出に対して水際で炭素コスト分の還付を行う場合もある。
これらはEU域内に工場を持ったり、EU域外の工場から域内に輸出を行う日本の製造業に直接的に影響を与えるだろう。
白土の7月のレポートによると、世界銀行のデータベースでは、2021年4月10日時点で46の国、35の地域でカーボンプライシングが導入されており、2020年時点で12ギガトン(CO2換算)の排出量をカバーし、これは全世界のCO2排出量の22.3%を占めている。
「一般に、高い炭素価格が設定されればされるほど、脱炭素のための投資意思決定のハードルが下がり排出量削減へのインセンティブが働くといわれるが、各国でカーボンプライシングの導入の動きが進むとともに、炭素価格の高騰が進んでいる。EU Emissions Trading Systemにおける排出権の価格は、2020年4月6日から2021年3月26日までの期間で、最低価格18.58ユーロから最高価格42.72ユーロまで高騰している」と白土は書いている。
ESG投資の潮流の影響
ESG(環境、社会、ガバナンス)投資もまた、株主からの圧力という側面で日本企業に影響を与える可能性がある。
2006年に国連より発表された「責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)」の中で、ESGの重要性が示されたことによって、ESG投資が主流化し、2015年には世界最大の機関投資家である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が同原則に署名した。
近年、ブラックロックのような超大型ファンドや各国の年金基金は「Climate Action 100+」という投資家イニシアティブに参加し、「世界でも最も環境に影響を及ぼしている上場企業167社(日本企業10社を含む)」にネットゼロの戦略を求める書簡を送付するなど活発な活動を見せている。
彼らは気候変動への対処を怠っていると判断された石油会社の取締役会メンバーの刷新を迫る戦略的な投票を行ったりと、ときにアクティビスト的な動きを見せるようになっている。日本企業の大半は外国人投資家の保有割合が限られたものではあるものの、この種のリスクに日本企業が露出することは無きにしもあらずだ。
PwC Japan シニアマネージャーのピヴェット久美子は「以前は企業に対し情報の開示を求めるという方法が取られたが、より積極的なアクションを引き出すためのツールを使うようになっている。日本企業はESGへの取り組みに関する情報を開示するコミュニケーションの導入を進める必要がある」と話した。

※本記事はPwCのメディア・イベント「2021調査結果発表:米中欧3極間の緊張関係に伴い急速に高まる日本企業の『経済安全保障・地政学リスク」』への意識」の取材によるもの。