HBOは2006年にNetflixの買収を検討していた
HBOは2006年にNetflixの買収を検討していた。しかし既存ビジネスとの衝突を気にする経営陣が見送った。もう少しでダイヤモンドの原石を手に入れられるところだった。

要点
HBOは2006年にNetflixの買収を検討していた。しかし既存ビジネスとの衝突を気にする経営陣が見送った。もう少しでダイヤモンドの原石を手に入れられるところだった。
NetflixがHBOの番組制作の方法を模倣したのはよく知られている。2013年にNetflixがローンチした「ハウス・オブ・カード」は、有名な監督が制作し、有名な俳優が出演する、豪華な大作コンテンツで、HBOスタイルのコンテンツだった。これ以降、NetflixはHBOスタイルのコンテンツを大量投入し、現在の成功につながった。
ESPNや『サタデー・ナイト・ライブ』などと関わってきたジャーナリストのジェームス・アンドリュー・ミラーが新たに執筆したオーラル・ヒストリー本『Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers』は、HBOが2006年にNetflixの買収を検討していたことを明らかにしている。
Netflixがストリーミングビジネスに参入する2年前の2005年、HBOの幹部たちは、ストリーミングへの参入を真剣に検討していた。彼らは、HBOがケーブルテレビの大手配信会社に商品を卸すのではなく、インターネットを使って消費者に直接、視聴料を販売することを望んでいた。
1年後、このアイデアを見送った後、HBOはメディアの歴史を塗り替えるような別の動きを検討した。HBOの幹部の中には、当時10億ドル程度の価値しかなかったDVDレンタルメール事業者のNetflixをHBOが買収することを望む者がいたのだという。
「2005年に大きな会議があったわけだ。それは、HBOが消費者への直接販売に関して、文字通り道の分かれ道を見つめていた瞬間だったからだ」とミラーはRecode Mediaのポッドキャストで語った。「2005年、この会議では2つのことが行われていた。1つは『消費者に直接販売しよう』というもの。もう1つは、『Netflixを買おう、彼らは我々ができないことをやろうとしているからだ』というものだ。そしてそれは、自分たちを差別化するためのさらなる手段となるだろう』というものだった」。
ミラーは続けて、幹部たちはこのアイデアのどちらも実行に移すのをためらったと語った。上層部は、ケーブルテレビ会社との関係が悪化することを恐れていた。彼らの頭の中には、消費者に直接販売する実験によって、HBOの通常の収入源が失われることがあるということがあった。ケーブルテレビとHBOは、HBOの設立当初からパッケージ化されており、ストリーミングをするためには越えなければいけない壁があった。
HBOは2005年にチャンスがあったにもかかわらず、ダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)を採用しなかった。ジェームズ・ミラーはたとえHBOがNetflixにアプローチしたとしても、Netflixが売却するかどうかはわからないと考えている。しかし、Netflixは2000年に米国最大ビデオレンタルチェーンBlockbusterに会社を売却しようとした。
Netflixが正式にサービスを開始してからわずか2ヵ月後の1998年の夏には、Amazonのジェフ・ベゾスと事業売却の交渉を行っている。
シアトルの「豚小屋」のようなAmazonオフィスでの会議終了後、ベゾスのチームはNetflixに「8桁台前半」の買収金額を提示したという。当時のCEOのマーク・ランドルフは「それは、おそらく1,400万ドルから1,600万ドルの間だと思う」と回想している。
Netflixは現在、約3,000億ドルの価値がある。そして、Netflixのような独自のサービスの販売を2015年まで開始しなかったHBOは、Netflixだけでなく、Disney+、Peacock、Amazon Prime Videoなど、数多くのストリーミングサービスの競合他社に追いつく必要に迫られている。一方、HBOの親会社は、M&Aのせいで、この3年間で3回も変わっている。
2005年にHBOとその親会社であるタイムワーナーが、当時、HBOの番組を消費者に直接販売することを決めたとしても、それは成功しなかったかもしれない。当時、米国のほとんどの家庭にはまだブロードバンド・インターネットが普及していなかった。さらに言えば、当時HBOが配信を頼りにしていたケーブルテレビ業界は、HBOが離反しないように必死に戦っただろう。
一口15万円の投資を受け付け中
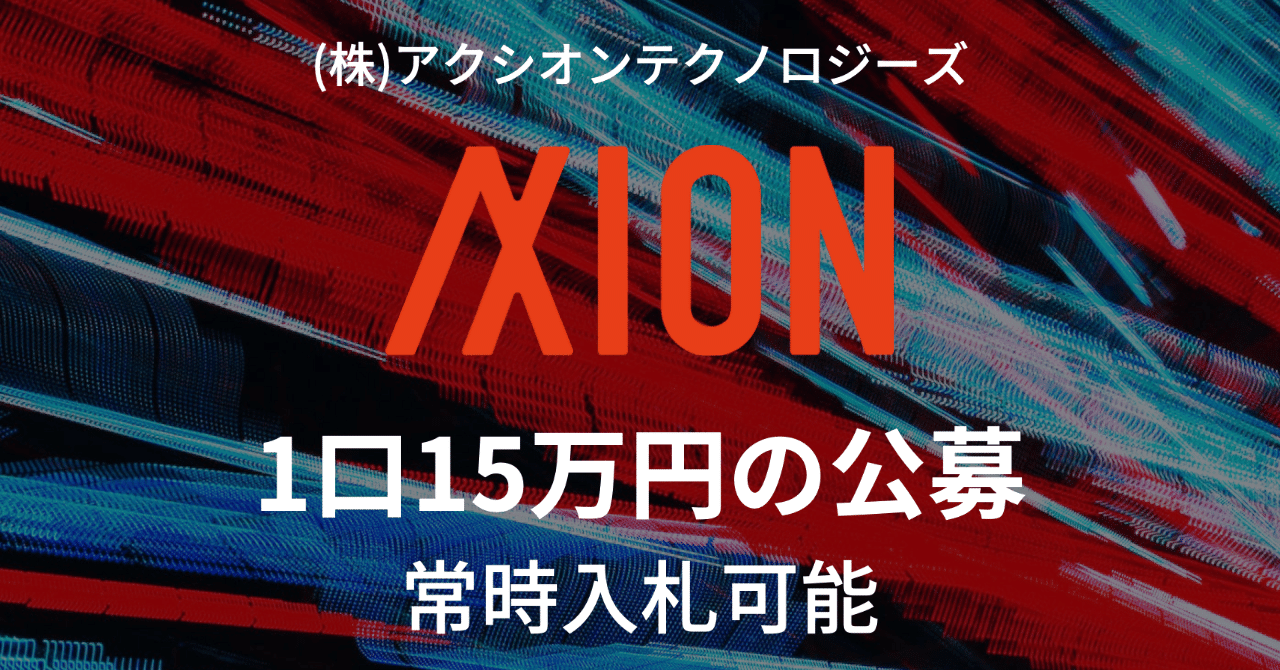
クリエイターをサポート
運営者の吉田は2年間無給、現在も月8万円の役員報酬のみ。
BTCアドレス:3EHYZm8hyCRyM1YSrF97dq8a25t5c2wJy9










