トランプを熱狂的に支持した絶望する白人の素顔 :『ヒルビリー・エレジー 』
著者が描くのは、住民の3分の1が貧困にあり、離婚や暴力沙汰、薬物依存症も珍しくない、中西部の「死んだ町」の実情です。このような町に取り残された「絶望した白人」が、トランプを支持したのです。
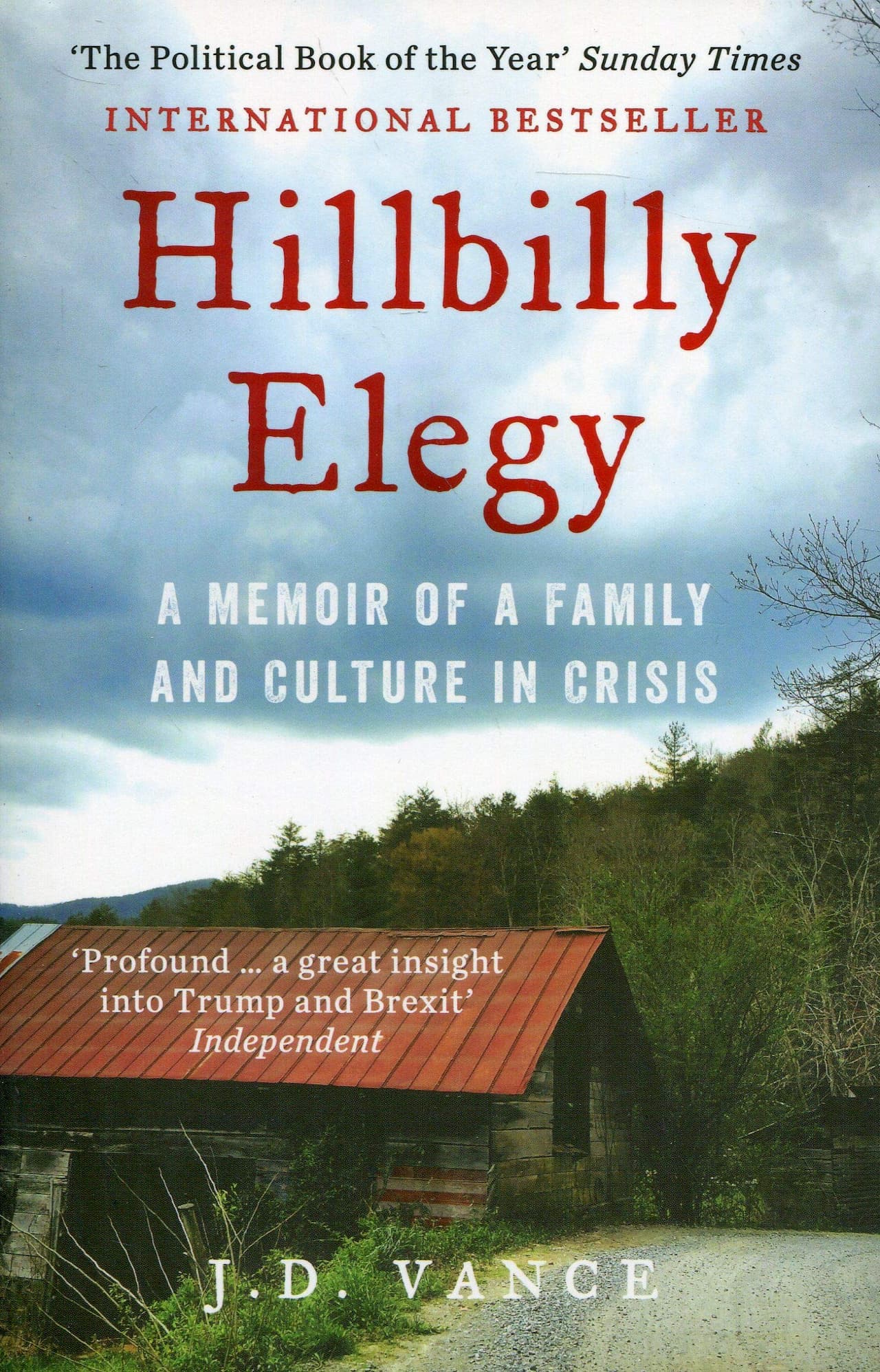
2016年6月に出版された回想録の原書はアメリカでベストセラーとなり、同年9月の大統領選では、「トランプ現象」を説明する書籍として注目を浴びました。出版社のHarperCollinsによると、最初の印刷が1万部のこの本は、トランプが大統領選挙に当選した後、ハードカバー50万部とデジタル版およびオーディオブック28万部を販売しています。
本書は回想録であり、貧困か貧困に近い状況に苦しんでいる白人がトランプを押し上げたことを定量的に示すものではないものの、そこに存在する社会構造を示唆します。
著者のJ.D.ヴァンスはオハイオ州の寂れた町出身の「ヒルビリー(田舎者)」であり、高校卒業後に海兵隊、州立大学、イェール大学ロースクールに進んで成功しました。卒業後はベンチャーキャピタリストの道を歩んでいます。彼はピーター・ティールのミスリルキャピタルマネジメントのプリンシパルとして、最近ではRevolutionのマネージングディレクターとして働き、2020年1月、オハイオ州シンシナティに本拠を置く、中西部に焦点を当てたベンチャーファンドNarya Capitalを創業しています。
この回想録は、アパラチアとラストベルトの貧しく、そして怒っている白人アメリカ人の置かれている状況について記述しています。住む家を転々とせざるをえなかったヴァンスの故郷の1つであるケンタッキー州ジャクソンでは住民の3分の1が貧困にあり、離婚や暴力沙汰、薬物依存症も珍しくありません。ヴァンス自体も産業が荒廃し、崩壊の危機に瀕する過酷な環境のなかで育ちました。12歳のとき実の母に殺されかけ、母を被告とした裁判に出廷しており、彼を取り巻く家族もまた、怠惰、暴力、ドラッグの何らかに人生を毀損されています。
著者は「学習性無力感」という言葉に何度か言及しています。これは、長期にわたってストレスの回避困難な環境に置かれた人や動物は、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなるという心理学の考え方を指します。「学習性無力感」がヒルビリーと呼ばれる白人に蔓延しており、内部から彼らをむしばんでいると、筆者は推測しているのです。

ヴァンスは町からは希望が失われており、そのような社会状況が人々の行動に深刻な影響をもたらしている様子をこのように記述しています。
「タイル会社の倉庫で私が目にした問題は、マクロ経済の動向や国家の政策の問題よりも、はるかに根が深い。あまりにも多くの若者が、重労働から逃れようとしている。良い仕事であっても、長続きしない。支えるべき結婚相手がいたり、子どもができたり、働くべき理由がある若者であっても、条件のよい健康保険付きの仕事を簡単に捨ててしまう」「さらに問題なのは、そんな状況に自分を追い込みながらも、周囲の人がなんとかしてくれるべきだと考えている点だ。つまり、自分の人生なのに、自分ではどうにもならないと考え、なんでも他人のせいにしようとする。そうした姿勢は、現在のアメリカの経済的展望とは別個の問題だといえる」(P.15)
著者は、高校の初めまで明らかに希望を失いそうな境遇にありましたが、その後数年で人生の大転換を果たすことに成功しています。しかし、本書を読む限り、彼が外れ値なのは明らかです。
生まれてくる環境は選ぶことができず、それが決定的にその人の将来を決めるとすれば、公平性を担保することはできません。近年、米国人の余命が短くなっており、働き盛りの人たちの死亡率が高くなっています。その中で、地方に住む白人層が薬物中毒やアルコール依存症、それに自殺といった、いわゆる「絶望死」をしていることに注目が集まっています。トランプの当選はピークを象徴しているのではなく、始まりの徴候にすぎないのかも知れません。
『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』J.D.ヴァンス 光文社
Image Via HarperCollins





