リスクに身をさらせ「失われた30年」を招いた日本のエリートに欠けているもの
日本では30年間経済の停滞が続いており、政府・官僚・日本株式会社は失敗を繰り返してきた。そのリスクを残念なエリートたちは背負ったことがあっただろうか。いや、ないのだ。
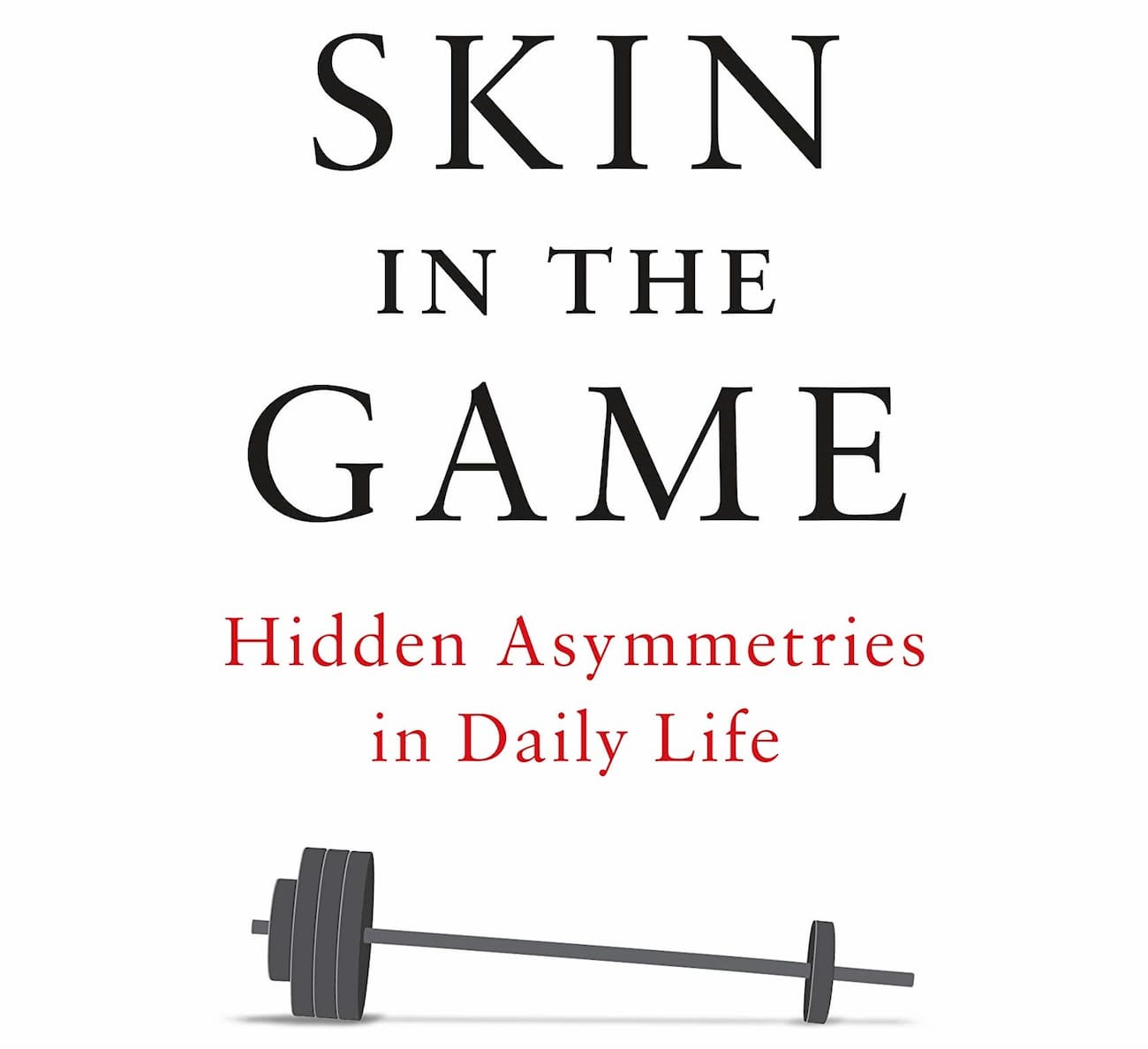
2007~08年に世界金融危機が起きて世界経済に深刻な影響が生まれた。調子に乗りすぎた銀行が生み出した大損は、納税者の金で救済され、世界中で関係のない人たちのビジネスが破綻し、失業者が溢れた。人生が変わってしまった人はたくさんいる。
大銀行がつぶれると、経済に深刻な影響が及ぶ。だから政府は金融危機に際し、莫大な公的資金をつぎ込むのだ。これは事実上、政府による銀行の債務保証である。投資や貸付けにはリスクがつきものだ。賭けで大損したときのことを考えてみよう。このとき政府は債務を肩代わりしてくれるものであれば、銀行は必要以上に大きくかけようとする。勝った場合の収益は銀行のものになり、負けた場合のつけは政府、つまり納税者が払ってくれるからである。
これはリスクとリターンの非対称性と呼ぶことができる。「勝ったらその果実は俺のもの、負けたらその責任は他人がかぶる」。このような環境に置かれた人間が合理的に行動することはまったく期待ができない。
ということで解決策がいくつかある。銀行に対して課されたのが「銀行に総資産に対して20〜30%の自己資本を持つよう義務付けることで金融システムの安全性と健全性は大幅に高まる」という考え方である。バーゼル合意とは、バーゼル銀行監督委員会が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統一基準である。バーゼル合意は、1988年に最初に策定され(バーゼルI)、2004年に改定されました(バーゼルII)が、世界金融危機を踏まえて、バーゼルIIIが2017年にバーゼルIIIは世界各国において2013年から段階的に実施されており、最終的には、2027年初から完全に実施される予定になっている。
バーゼルⅢでは、銀行が想定外の損失を出した場合でも経営危機に陥ることのないよう、自己資本比率規制が厳格化された。また、急な資金の引き出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率規制等が導入されることになった。自己資本比率はレバレッジの逆数であり、高率の自己資本比率規制を行えばレバレッジが減り、上下両方、すなわち、利益率も損失率も低下することになる。金融危機の防止策としてはそれなりの有効性があるけれども、同時に、銀行業界の利益率を低下させる可能性もある。銀行業界の利益率の低下がそれほど憂慮すべきものかというと、大恐慌のダメージと引き替えにするまで守るものでは決してない。
では、これで世界は恐慌に万全たる準備を終えたかというと、そうでもないかもしれない。世界規模の大恐慌は1980以降、1980年代初頭、90年台初頭、ドットコムバブルの2001年、2007-08年の計4回起きており、前回から10年経ったので「また起きるのではないか」と言われている。
バーゼルⅢを含むレギュレーションが根本的に状況を変えたかと言えば、そうではない。The Economist によると、cross-border financial claims (銀行や法人が登記された国家の外との人物やエンティティとの間で結ぶローン、債権、支払いのこと)は30兆ドルに達している。2008年のピーク時の35兆ドルには達してはいないが、1998年の9兆ドルの3倍以上の水準にあるのだ。国家が金融機関を規制の枠内にはめ込むのは難しく、世界の金融機関の相互依存性は深いままを維持しており、言い換えれば10年前と同様に危機が伝播しやすい状況とも言い切れるかもしれない。これらについては高名なエコノミストで意見が割れているが、結局のところ起こってみないとわからないという状態なのだ。金融危機以降何度も非難の的にされたシャドーバンキングは依然として規制の外にある。金融機関だけでなく事業会社などもシャドーバンキングシステムの活用に勤しんでおり「無くしたくとも無くせない」ものとして存在し続けている。
さて、リスクとリターンの非対称性の話に戻って来て、僕が紹介したいのは、ナシム・ニコラス・タレブの”Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life”だ。タレブは金融危機の状況を詩的で装飾的な文章で描写した『ブラック・スワン』で有名だ。ブラック・スワンとは予期せぬものの象徴であり、正規分布からはかけ離れた事象が正規分布に基づいた戦略を取るプレイヤーを撤退させてしまう突如生まれる巨大なリスクについて書かれている。ある人がゲームの中に投じているリスク(Skin in the Game)が大きければ大きいほど、ブラック・スワンを被る可能性が高くなる。その人にシステミックな崩壊を避けるという合理的な行動を強く促すことになる。タレブは専門家の言うことを疑うことを推奨している。「彼らが言うことや何をしているかだけに注意をはらってはいけない。どれくらい彼らの首が線上に置かれているのかを注視すべきである」と指摘している。
タレブは利益を手にするにはそれと対称のリスクを取る必要がある、そのリスクを他人に転嫁するべきではないと主張している。”Skin in the game”の状態が倫理的に善であり、社会全体でも脆弱ではない求められる状態である、と説明する。
この指摘は素晴らしい。日本では30年間経済の停滞が続いており、政府・官僚・日本株式会社は失敗を繰り返してきた。そのリスクを残念な日本のエリートたちは背負ったことがあっただろうか。日本でもこのリスクとリターンの非対称性が見過ごされている限りは、何度でも自称エリートたちは失敗し続けるだろう。失われた10年は、20年、30年と延び延びになり、その高いスケーラビリティ(拡張性)を誇っている。次は”失われた40年”を目指すときだ。





