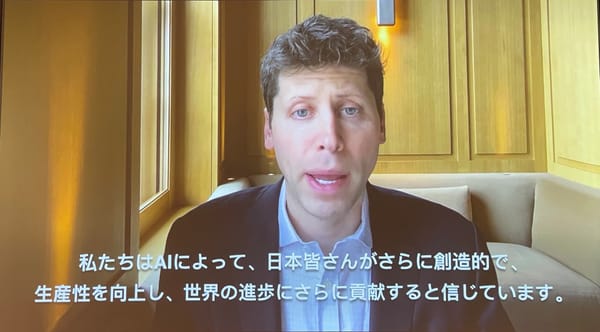ソフトバンクGのシュレーディンガーの猫:ブラックボックスの中の未上場ユニコーンは無事か?
ソフトバンクグループ(SBG)の命運は、ブラックボックスの中にある数多の未上場株次第だ。同社が買い漁ったユニコーンは生きているのか。これは「観測するまで事象の状態は決定されない」という「シュレーディンガーの猫」を想起させるものだ。
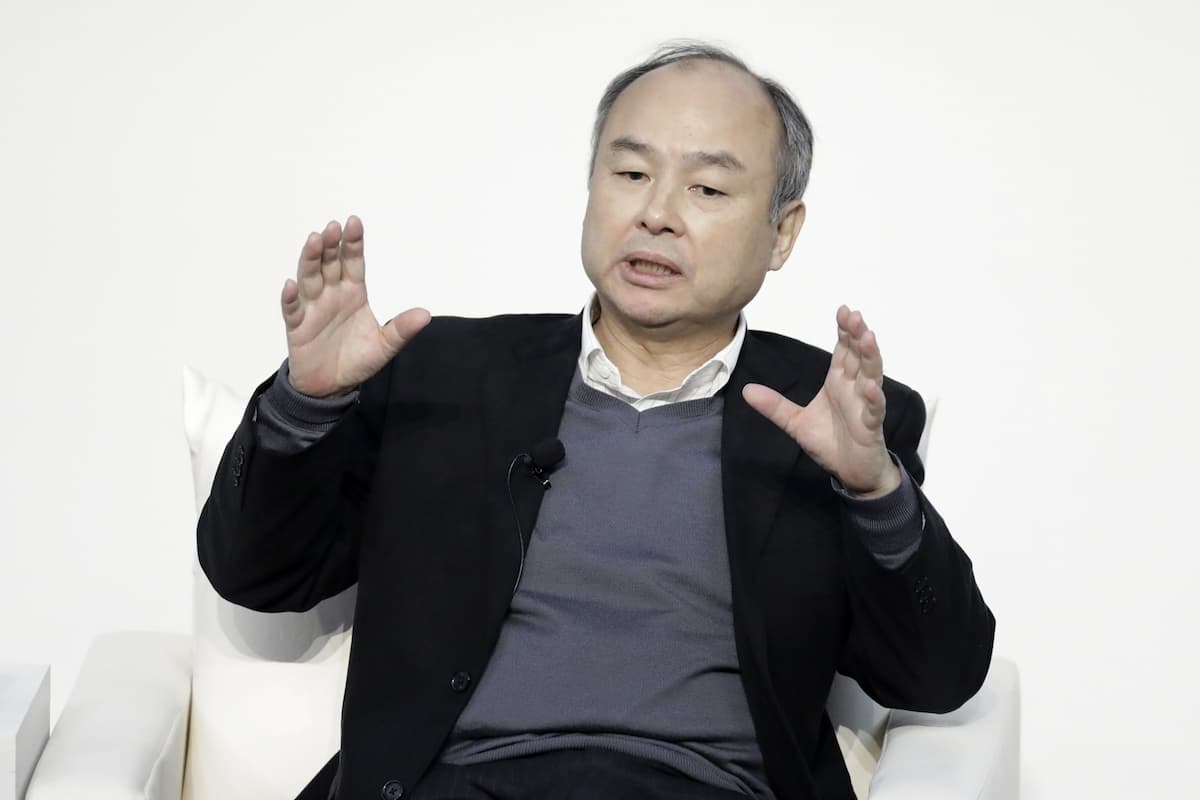
ソフトバンクグループ(SBG)の命運は、ブラックボックスの中にある数多の未上場株次第だ。同社が買い漁ったユニコーンは生きているのか。これは「観測するまで事象の状態は決定されない」という「シュレーディンガーの猫」を想起させるものだ。
「シュレーディンガーの猫」は物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが1935年、量子力学のコペンハーゲン解釈の問題点を説明するために、アルベルト・アインシュタインとの議論の中で考え出したものである。シュレーディンガーは、密閉された箱の中に、猫、毒の入ったフラスコ、放射性物質が置かれていることを想定していた。内部の測定器が放射能を検出すると、フラスコが割れて毒が放出され、猫は死んでしまう。
アインシュタインと論争をしていたニールス・ボーアの解釈では、猫は生きていると同時に死んでいることになる。しかし、箱の中を見ると、猫の生死は確定する。これは「観測するまで物事の状態は確定しない」という考え方に則っている。
シュレーディンガーはこの思考実験をボーアの考え方を批判するために考えだした。「私たちがわかっていないだけで箱の中ではすでに決定されているはずだ」というのがシュレーディンガーとアインシュタインの共通した意見だった。
未上場株の「猫」
さて、SBGの中核事業であるファンド事業もまたこのシュレーディンガーの猫との類似性が指摘できそうだ。ファンドの保有株の多くは、時価のつけられる公開株と異なり、価値算定の難しい未上場株である。これが「箱の中の猫」に当たるだろう。
ただ、SBGの猫は少し様子が違う。この未上場株は、箱の外側から見ると、さまざまな状態が同時に存在しているふうだが、箱を開けて観測しても、依然として複雑で、さまざまな状態が同時に存在し続けるだろう。「観測しても物事の状態は決定しない」という特異なものなのだ。
SBGの決算発表では、ファンド事業の情報は限定的であり、猫の生死を決定しない。ブラックボックスの中から、予測不能な形で損益が出てきて、それが損益計算書を大きく揺すぶる、というふうだ。
この1年ほど、多くの損失がファンド部門から計上されたが、類似ビジネスとの比較から未上場株のバリュエーションの切り下げが不十分との見方もある。そもそも、SBGには企業価値を切り下げるインセンティブが薄い(損失が確定するまで大きく見せたほうが得である)ため、実際はもっと深いラインまで沈み込んでいるものの、未実現損失を放置しているという観測は有望である。
未上場のユニコーンを巡る環境は芳しくない。新規株式公開(IPO)が低迷するせいで、孫正義会長の買い集めたユニコーンは出口を見つけることができない。金利の急上昇が資本市場から「タダ金」を一層し、シリコンバレーバンク(SVB)というスタートアップ専門の負債を提供していた地方銀行が破綻した。ユニコーンはバリュエーションの切り下げを避けるため負債調達を選択してきたが、負債のコストが高くなっている。
SBGは2021年のブーム時に上場寸前の段階のスタートアップに数多く投資し、それらが2022年のテック株の大調整の中で出口を失ったことから、ベンチャーキャピタル(VC)の中でも最も大きな企業価値の切り下げを強いられていると推定することは自然である。実際、2022年から大手VCの関心は、株式市場の影響を受けづらいアーリーステージ(初期段階)のスタートアップへと移行したこともレイターステージ(後期段階)の「塩漬け」を説明しうるものだ。
NAVとLTVは改善したようだ
「箱の中の猫」の情報を探る上で、SBGが経営指標とする純資産価値(NAV)とLoan to Value(LTV)は一定の利用価値がある。
私の独自の算定では、NAVは9.3兆〜10.3兆円、LTVは12%〜53%で推移している。SBGが公表するNAVは15.7兆円、LTVは11%である。私の独自算定は純資産と純負債の範囲がSBGの設定する枠と異なり、英当局への提出書類を基にした報道をベースにソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)1の成功報酬の構造も織り込んでいる(*1)。これについては、私は以下のブログで詳しく説明した。

また、過去3四半期の算定のプロセスは以下のスプレッドシートに公開してある。
株式先渡契約はほぼ「売った」とみなすべきと考えられるため、控除されるのが妥当だろう(契約を維持するコストが生じ続けるが)。今四半期で「最も有力なLTV」は37〜39%のレンジにあると考えていいだろう。
資産売却と現金の積み増し
箱の外側の重要な要因として、SBGの資産売却と現金の積み増しがある。独立採算子会社であるソフトバンクと「その他項目」を除いた現金と現金同等物は4.2兆円に達した。
資産の切り売りが進行中だ。SBGは今年株式先渡契約を通じてアリババ株式を売却したと報じられ、残されたアリババ株の価値は7,000億円相当となった。傘下の資産運用会社フォートレスはアブダビ首長国の政府系ファンド、ムバダラに最大30億ドルで売却する交渉が佳境に入ったとブルームバーグが報じた。担保に入っている英半導体企業Armの流動化も近づいているようだ。
4月初旬に個人向けにシビアな条件の社債を発行し、同社は最近の決算説明会では「守備」のワードを連発してもいる。
これらの動きの背後にあるのは、世界的な金利上昇が、同社の資本コストを大幅に引き上げたことではないだろうか。
同時に、銀行不安の煽りを受けて、投資先のスタートアップがレスキューファイナンスを必要とするシナリオに備えているように見える。SBGは過去にも、破綻した英貸金業者グリーンシル・キャピタルを通じて、経営難に見舞われた建設会社のカテラやホテルチェーンのオヨのような支援企業に資金注入したことがある。この支援スキームの一環でSBGはクレディ・スイスの顧客の利益を毀損した可能性があり、英国で訴訟が始まろうとしている。
クレディが被ったと主張している損害については、以下のブログで説明している。SBGは決算発表会で「訴訟に勝てる」と述べている。

結論
結局、箱を開けてもあまりにも不確実性が高く、猫がどうなっているかは判断はつかないだろう。それでも、「箱の中の猫」の状態を知っているSBGの動きを見れば、猫は弱っているか、もっと弱ることになる可能性は高いように見える。もちろん、2021年のような楽観性を市場が取り戻すなら話は別だ。
脚注
*1 : 私はSVF1のリターンについて公開情報と報道を基に推定を入れたバージョンのNAV、LTVも算定している(スプレッドシート参照)。ただし、SVF1のファンド構造については、SBGによる公開情報と報道である程度の概要が明らかになっているが、すべての情報が得られているわけではない。