SNSは後進に道を譲れ
Twitter元幹部による内部告発はSNSに「最後の一撃」を食らわせたように見える。SNSはモバイル化の波に乗って人々の可処分時間を占領したが、トレンドの転換とその負の側面に注目が集まったことで、再浮上の契機はなくなった。
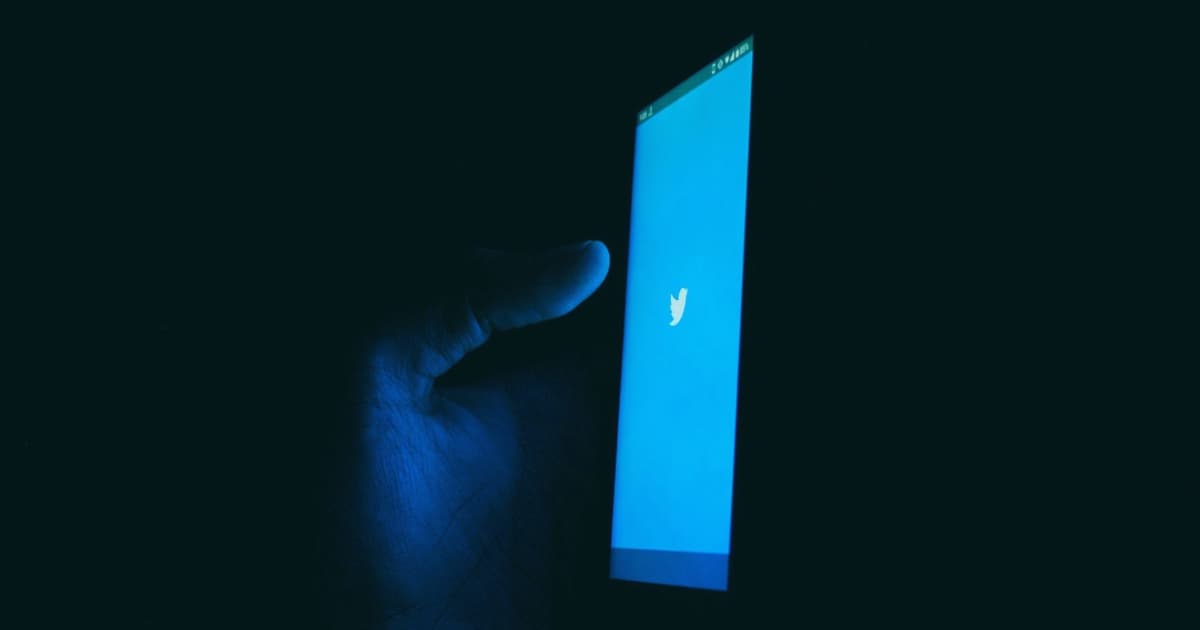
Twitter元幹部による内部告発はSNSに「最後の一撃」を食らわせたように見える。SNSはモバイル化の波に乗って人々の可処分時間を占領したが、トレンドの転換とその負の側面に注目が集まったことで、再浮上の契機はなくなった。
TwitterのCEO直属の最高セキュリティ責任者だったピーター・ザトコが内部告発を行った。告発の内容は200ページ超の報告書にまとめられ、当局に提出されたという。

これは、買収に合意した後にTwitterの情報開示を非難し、買収完了をしようとせず、Twitterに訴えられたイーロン・マスクにとっては、願ったり叶ったりの内部告発となった。
マスクの弁護士は、ザトコを証言台に立たせるつもりだ。ザトコが内部告発の内容を法廷でなぞり、Twitterが敗訴し、一部始終が報道されることで会社のモメンタムが完全に失われる―そういう最悪シナリオが浮かんでいる。
この内部告発は昨年行われたFacebookの元データサイエンティスト、フランシス・ホーゲンによる内部告発に続くものだ。Facebookはその数週間後にMetaに社名変更し、「SNSの会社」というレッテル自ら剥ぎ取った。
このときすでにマーク・ザッカーバーグはSNSが退潮していくことを社内の非公開のデータから理解していたというのは穿った見方ではないだろう。Facebookの利用者が高齢化し、アクティブ性が低迷しているのは、数年前から公然の秘密だった。
Facebookはコンテンツ消費の場がモバイルへと移っていくことの旗手だった。同社はモバイルにおけるHTML5の可能性を探り、ユーザーは当時恐ろしく不便だったモバイルウェブを一生懸命使っていた。ザッカーバーグがネイティブアプリを重視する戦略にかじを切ってから、Facebookはスマートフォンの王者となった。
2010年代半ばまで欧米圏のSNSでは、「このドレスは何色ですか?(What Colors Are This Dress?)」という錯視をめぐる、とりとめないのない記事が世界的にシェアされる牧歌的な時代だった(下は前職時代に執筆した記事)―実際には新興国ではすでにSNSを使った政治や社会への攻撃が当たり前のように行われていたのだが……。

当時珍しくなかったグローバル・バズは、FacebookやTwitterにとっては格好のユーザー獲得手法だった。しかし、ユーザー獲得がサチってくると、最高設定のスロットマシーンのように「バイラル」を引き起こしまくるアルゴリズムのいろんな副作用が気になってきたようだ。偽情報や倫理を逸脱した投稿のようなまずいものがものすごい勢いで流布していく様子をFacebookの中の人は見る羽目になったのだろう。それが最終的に未曾有のスキャンダルへと繋がり、それ以降も状況は悪化の一途にある。

FacebookやInstagramから天下の座を奪い取ったTikTokは、厳密にはソーシャルメディアではなく動画アプリケーションである。TikTokが使うコンテンツレコメンドの手法は、FacebookやTwitterのようなつながりに依存していない。むしろ、このような手法をいまFacebookやInstagram、Twitterが取り入れ始めている。
トレンドは変わった。最も若い世代のファーストチョイスにSNSは入っておらず、彼らはそれを高齢者の嗜みだと考えている。
これらを反映するかのようにSNS企業の株価は低迷している。Snap、Twitter、Pinterestなど、米国の大手ソーシャルメディア企業の多くは、現在、上場時よりも時価総額が下がっている。Metaの株価は現在、史上最高値の半分以下で取引されている。
次の人々のコミュニケーションの場として期待されるメタバースは、まだ道半ばだ。Facebookはデバイスとプラットフォームを押さえる戦略をとるために100億ドルを超える投資をこれまでしてきた。
しかし、エピックゲームズのような長期的にゲーム産業に投資してきた企業と比較すると、アンリアルエンジンとフォートナイトの組み合わせのような戦略的優位性はまだ確立できていない。
しかも、知り合いのアイデアの盗用や「有望な新人」を片っ端から買収することによって、トレンドを捉えてきたMetaは、コンシューマをワクワクさせることには余りにも慣れていない。それは、先週世界を賑わした、ザッカーバーグの衝撃的な「メタバース内自撮り画像」で再び明らかになった。

さて、Twitterの命運はマスクとの裁判にかかっている。ここでうまく勝訴し、マスクにその身を委ねることができたなら、命綱を掴んだと言えるだろう。だが、うまく行かなかった場合、残酷ではない未来を想像するのは難しい。
SNSはその登場から十分長く活躍した。いまは後進に道を譲るときだろう。







