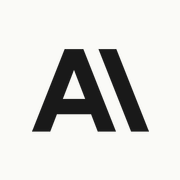アマゾン、AIの出遅れを取り戻すためM&Aに注力か?
アマゾンが生成AI新興企業への投資に40億ドルを使った。AIがクラウドの主要な成長源になる中、同社の研究開発は遅れているとみなされており、溝を埋めるための投資や買収合併が今後も行われる可能性がある。

アマゾンが生成AI新興企業への投資に40億ドルを使った。AIがクラウドの主要な成長源になる中、同社の研究開発は遅れているとみなされており、溝を埋めるための投資や買収合併が今後も行われる可能性がある。
Amazonは、AIスタートアップのAnthropicに最大40億ドルを投資することに合意した、と発表した。投資契約の一環として、Anthropicは安全性の研究や将来のAIモデル開発など、必要不可欠なワークロードにAmazonのクラウドサービスAWSを利用する。将来的にはAmazonの生成AIサービスにAnthropic製品が組み込まれるようだ。
Anthropicの主要な製品は、AIチャットボット「Claude」である。Claudeは、要約、検索、クリエイティブな共同執筆、Q&A、コーディングなどのユースケースを支援する。Claudeは有害なアウトプットを出す可能性が非常に低く、会話しやすく、より舵取りがしやすいので、より少ない労力で望むアウトプットを得ることができる、と初期の顧客が報告している、とAnthropicは主張している。Claudeは、性格、口調、行動についても、ユーザーの指示を受けることができる。

大規模言語モデル(LLM)の競争では、米大手テクノロジー企業と中国勢とUAEとサウジが第一階層を争っている。この軍拡競争に追随できている新興企業は、ChatGPTのOpenAIと、DeepMind共同創業者のムスタファ・スレイマンのインフェクションAI(Inflection AI)のみと考えられている。計算に伴う巨額の費用と、NVIDIAのGPUの保持と入手可能性が、大きな堀となっている。米テクノロジー業界では、GPU富豪とGPU貧民に世界が二分されたという言説がヒットした。
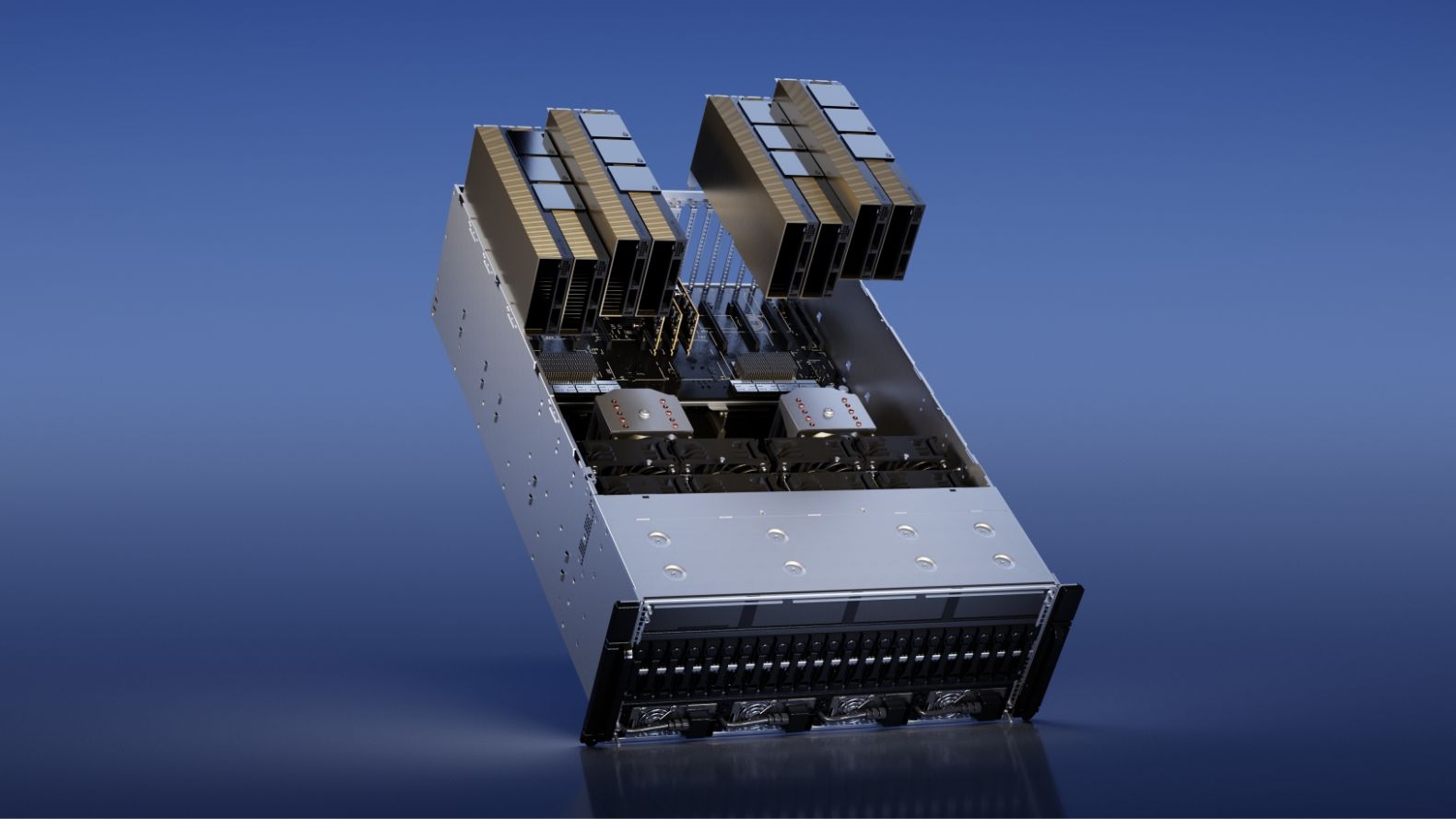
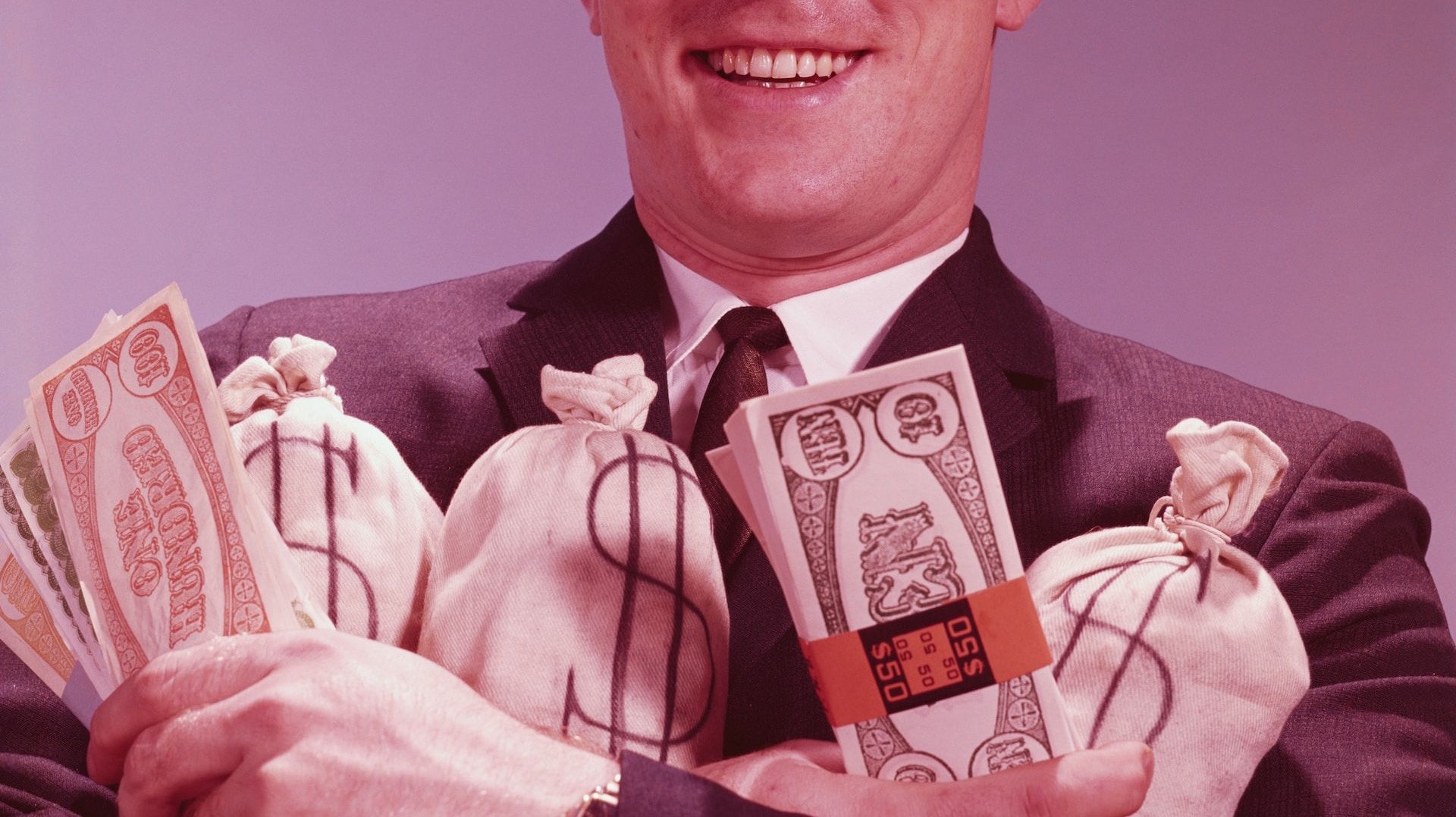
Anthropicは、エンタープライズに響く「安全性」を全面に押し出すことで、カスタマーサービスなどの分野への浸透を急ぎ、計算集約的(コンピューティングコストがものすごくかかる)なLLMの軍拡競争で独自のポジションを模索している。
背景
投資の背景には、クラウドプロバイダー間の熾烈な競争がある。市場調査会社ガートナーの予測によると、世界のクラウド・サービス市場は、昨年の4,910億ドルから今年は5,973億ドルへと、前年比21.7%増の成長が見込まれており、生成AIのブームが少なからずその原動力となっている。

Google Cloudは8月下旬に行った年次イベントで、AI開発・運用を簡単に行える機械学習プラットフォーム「Vertex AI」の対応モデルが100以上に増加したことや、様々な機能追加を発表した。この発表時点では、Google CloudはAIの提供能力でAWSやMicrosoft Azureに差をつけたと言える。

AWSは、おカネを使うことでこの差を埋める時間を短くしようとしているようだ。
AI機能の立ち遅れを持ち前の営業力でカバーできるか?
Amazonは、長期的にAI分野の研究開発を続けてきたGoogleとOepnAIを支援するMicrosoft、商用利用可能の「オープンソース」でAIを民主化するMetaと比べたとき、AIにおけるプレゼンスが欠けている。
しかし、AWSの顧客の大半は、生成AIのパフォーマンスを見抜く能力に欠けているはずで、似たようなラインナップがAWSにある限りは、AWS製品を選ぶだろう。システムの大半がAWSにロックインされている場合も、同様の引力が働くはずだ。
投資が意味しそうなこと
Anthropicには、Googleが今年2月に3億ドルの投資を発表していた。AmazonとAnthropicの投資契約は公開されていないが、40億ドルの金額を勘案すると、Amazonは最大の外部株主になったことは確か。他の投資家よりも有利な条件がAmazonに与えられている可能性もある。
もしかしたらGoogleにとって、Anthropicの優先順位は低いのかもしれない。 Googleをめぐる状況は、2月の投資から変化している。GPUを買い集め、Google BrainとDeep Mindを合併させた。合併の果実とも言えるAIモデル「Gemini」の提供を限定されたユーザーに対して始めていると言われる。Googleが通常の条件の付いた優先株主なら、Amazonの投資を阻むことができたはずだ。