キラーアクイジション 競合の芽を摘む電撃的買収
キラーアクイジション(キラー買収)は キラーアクイジション(キラー買収)は競合の登場を事前に抑えつけ、産業カテゴリの寡占を維持、または深める買収を指す。寡占傾向の強いテクノロジー・メディア・通信(TMT)業界における「ビッグテック規制」の中心的な話題のひとつだ。
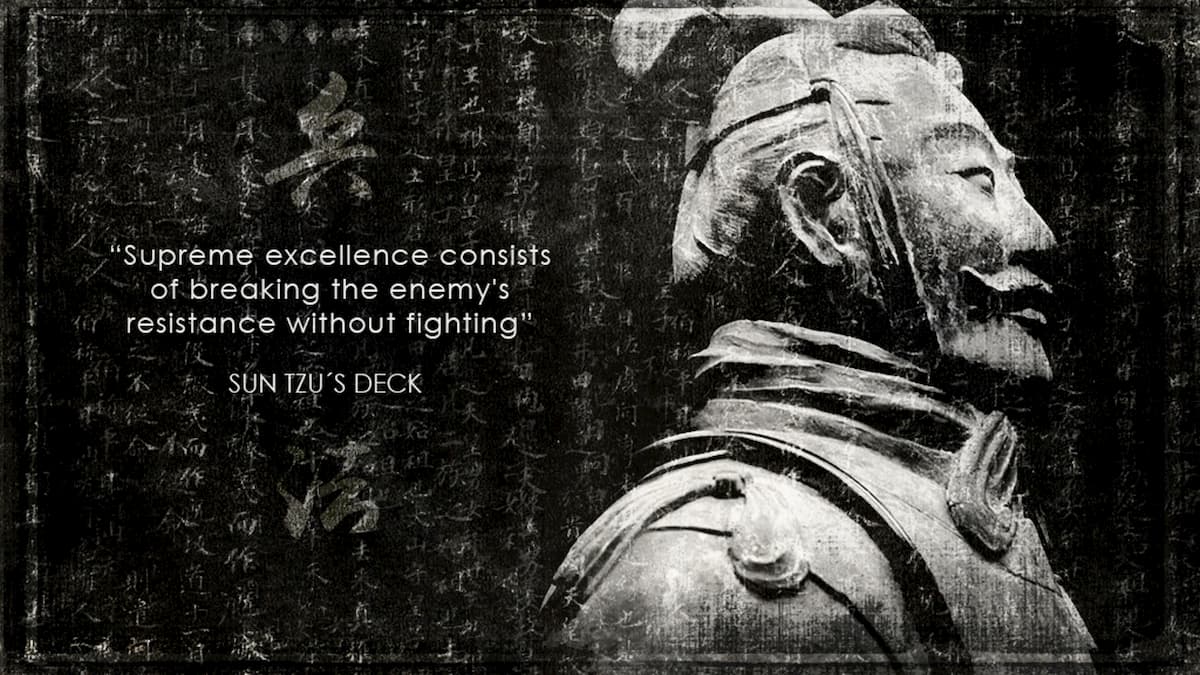
Facebookが潜在的なライバルであるInstagramやWhatappを買収し、買収された両者はその後大きく成長した。Facebookはこのおかげでコンシューマーインターネットで独占的な地位を固めた。もちろん、Facebookという会社自体がもともと持っていた力が奏効したことを考慮に入れないといけないため、単純化はできないが、結果としてFacebookは潜在的な競合の芽を摘み、その競合が楽しんでいたであろうマーケットとデータ収獲等の様々な機会を取り込むことに成功した。
この事例は利益率の高いテクノロジー企業が、蓄えたキャッシュにより巨額買収を繰り返すことで、「イノベーターのジレンマ」を回避することが可能であることを示している。Facebookのようなビッグテックの買収はいつも成功するわけではないが(マイクロソフトのノキア、Googleのモトローラなど)、一定の確率で当たりくじを引いていれば、競合の登場を事前に抑えつけながら、産業カテゴリの寡占を維持、あるいは深めることができる。
このような買収のことを「キラーアクイジション」(killer acquisitions : キラー買収)と呼ぶ。この決定的な買収の動機は、買収者とターゲット製品の重複が大きく、製品市場の競争が低い場合に強くなると想定される。
連邦取引委員会(FTC)の競争局は今年2月、米国のテクノロジー市場での競争を監視し、それらの市場での潜在的な反競争的行為を調査し、正当な場合に執行措置を講じることを専門とするタスクフォースの設立を発表した。このタスクフォースは8月から、FacebookによるInstagram(2012年)、WhatsApp(2014年)というキラーアクイジションの典型例への調査を開始している。
テクノロジー・メディア・通信(TMT)業界はすべての業界の中で最も寡占傾向が色濃い業界である。特にテクノロジー業界にはネットワーク効果が生じるカテゴリや、勝者総取りの傾向があるカテゴリが存在しており、合併買収は重要な経営戦略の選択肢にあたる。
近年はスタートアップ投資のエコシステムが発達し、小規模スタートアップが巨大化するまでの時間が急速に短縮されてきたことも、キラーアクイジションの誘因になっている。中国のソーシャルECの併多多(Pinduoduo)は創業からたった4年のうちに創業15年のJD.comの取引総額(GMV)を超え、 その時価総額は360億ドルに到達した。既存プレイヤーはこのような常軌を逸した速度で成長する新興企業を抑え込むためなら、古典的な損益計算書のみを基にした算定手法から到底導き出せない企業価値を提示することも吝かではない。
キラーアクイジションは必ずしも成功しなくともいい。ビジネスへの脅威を早期に摘み取ることは利得が大きく、また買収先がまだ始まったばかりの数人による会社の場合、人材獲得の傾向を帯びる。『世界で闘うプロダクトマネジャーになるための本 トップIT企業のPMとして就職する方法』(Gayle Laakmann McDowell、 Jackie Bavaro)はFacebookのスタートアップ買収の一側面についてこう説明する。
「Facebookは他社の従業員を雇用する目的でその会社を買収することがあり、これをacqui-hiring(訳注: 人材の獲得を狙って買収すること)と呼ばれています。人材の獲得を狙ってチームを買収する場合、Facebookは通常、10人未満、しかもその大半がエンジニアで構成される小規模なチームを狙います。その企業の設立者やCEOがプロダクトマネジャーとして迎え入れられることが、しばしばあります」。同社は「acqui-hiring」で同社の一員になったプロダクトマネジャーの「創業者経験」を高く評価することはよく知られている。

日本の公取委
公正取引委員会の「事務総長定例会見記録(令和元年10月9日付)」で、山田昭典事務総長は日本でもデジタルプラットフォーマーのキラーアクイジションへの審査を強化する方針を説明している。
「昨今,今御指摘のような案件が話題になっているということもありますけれども,デジタル分野においては,現在まだ市場においてはそれほど大きな存在ではないにしても,将来的に発展するかもしれない,特にデータを集積しているスタートアップ企業の芽を,大手の企業が摘み取ってしまうというところに,競争に対するリスクがあるのではないかというのは国際的にもホットイシューになっていると思います」
渡辺安虎・東大教授は、大手IT(情報技術)企業が持つ個人データの保護や市場支配力を巡る規制を強めるに当たり、規制する政府側に経済学者を増やすべきであると指摘している(日経新聞 2019/11/15)。
「巨大企業はデータ分析のできる経済学者チームを雇い、その分析結果に基づいて弁護士たちが法的な議論を組み立てる可能性が高い」とし、「実際に大手ITへの調査を担う米国の連邦取引委員会には、経済局に80人を超す経済学者が正規職員として在籍している。同じく司法省反トラスト局の経済分析グループでは50人を超す経済学者が正規職員として働く。合計150人に迫る経済学者が、合併審査をはじめ個々の案件審査に従事している」と説明する。
他方、日本は準備不足であるとの認識だ。「日本はどうだろうか。公取委に確認すると、経済学の博士号を持つ職員はわずか2人だという。法曹資格を持つ職員が32人であり、同じ専門家でも数の差が激しい。米欧の当局に比べるとデータ分析のできる人材の不足が深刻だ」
日本のTMT市場自体は飽和の感がある。現存企業はキラー買収や、ヤフージャパン(現Zホールディングス)とLINEの事業統合のようなLINEのそれのような寡占を形成するための合併により力を注ぐことになるだろう。公正取引委員会が反競争的な行いを防止することは市場に利益をもたらすだろう。
殺戮空間「キルゾーン」
近年盛り上がる反ビッグテックの議論の1つは、革新的なテクノロジー企業が実際に革新を打ち消しているということだ。ベンチャーキャピタリストはそれを「キルゾーン」と呼んでいる。
ビッグテックからのあらゆる種類の脅威に関するシカゴ大学での会議で、ベンチャーキャピタリストのAlbert Wengerがその理論を具体化した。彼の主張はこのようなものだ。
「GAFAのような企業の規模が、新興企業へ与える影響は巨大です。VCのポートフォリオ企業の創業者やCEOを結びつける年次サミットが昨年あり、VCの1人から出てきた言葉は『Facebook、Apple、Amazon、Googleのキルゾーンの外部にだけ投資することにしている』でした」。
「キルゾーンは新しいものではありません。Microsoftは、プラットフォームを独占したときにそれを実現しました。それはAmazon、Google、Facebookによって実行されているプレイブックでもあります。そしてすべての大きなデジタルプラットフォームによって実行されています」。
近年のデジタルプラットフォーマーの巨大化は圧倒的であり、Apple、Microsoft、Google、Amazon、Facebookの合計市場価値は5.5兆ドルを超え、東証一部のすべての企業の合算を超えている。ビッグテックに批判的な人は、大企業は合併買収を用いて、新興企業のビジネスが勢いを増す前に、場合によっては単にそれらを閉鎖するための「買い殺し」(キラーアクイジション)戦術を実行する、と指摘する。これにより、最も脅威となる可能性のある競合他社を市場から除外することが可能になる。GoogleとFacebookはこれまで何百もの企業を買収し、非常に頻繁にそれらを閉鎖しているのは事実大統領も。
5つの大企業は連邦取引委員会(FTC)の監視の下にありますが、テクノロジー市場の他の企業は、頻繁に、最も革新的な潜在的な競合他社を初期段階のうちに買収している。たとえば、5年前、SalesforceはRelateIQに3億9000万ドルを支払った。この新興企業の技術はSalesforce自体を飛躍させると見られていたからだ。
必ずしも、VC支援のスタートアップが全面的に大手企業に降伏するようになっているというわけではない。米国のVCは多量のお金を市場に注ぎ込み、満足のいく出口活動(イグジット)を遂げているように見える。PitchBookによると、2018年の米国のベンチャーキャピタル投資は1309億ドルに到達しました。ベンチャー支援の出口活動は4Qで沈静化したが、2019年通年の米国のVC出口活動時に創出された価値は、882の流動性イベントで2,564億ドルだった。
ビデオ会議ツールのZoomは米国のVCが好みそうな「想定外」だ。MicrosoftのSkype、GoogleのHangoutが先発していた市場に対して、後発のZoomは製品の品質を頼りに潜り込むことができた。Zoomは2019年のテックIPOのなかでも最も祝福されるべきパフォーマンスを示し、上場後も堅調に成長している。
2018年のコンサルタント会社オリバーワイマンによるベンチャーキャピタル投資分析は、特にFacebook、Google、Amazon(FGA)のVCへの影響を調査している。この調査はFacebookとの協力によって実施されている点に留意しないといけない。FacebookによるWhatsApp、Instagramの早期買収やライバルのSnapchatをコピー作戦で低迷させた戦い方は、まさしくコンシューマーインターネットに「キルゾーン」的を生み出している。
Facebookの依頼によって調査を行ったオリバーワイマンが指摘する重要なポイントは次のとおり。依頼主のFacebookにとって好ましい調査結果が並んでいる。
- グローバルなベンチャーキャピタル投資が引き続き大量にあり、昨年は約1500億ドルで、35%がテクノロジー企業に投資している。
- FGAによるベンチャー投資は、総投資額のわずか4%で、総技術投資に対して「比較的重要ではない」。
- FGAによるM&Aは、世界のテックM&Aの「ごく一部」に過ぎず、過去3年間のテックM&A活動全体の1%を超えていません。
- FGAが買収したハイテクサブセクターとそうでないテクノロジーサブセクターの成長率に実質的な違いはない。
- FGAの活動は、初期段階の投資家に追加の出口オプションを提供する。たとえば、2014年にFacebookがOculusを20億ドルで買収したことは、Andreessen Horowitzなどのベンチャーキャピタルに迅速かつ収益性の高い出口の機会をもたらした。

巨人に対し小人は無力
ただし、巨人がスタートアップを完全にコピーしなくても、大手企業は新興企業の見込みをくじくことができる。2017年、Amazonは食料品店であるWhole Foods Marketを137億ドルで購入した。Amazonがこのスペースに参入するという期待が高まったため、公開を準備していた食品配達のスタートアップであるBlue Apronは、突然、相対的な価値の低下に苦しみ、株式上場は不調に陥った。その後も従業員による訴訟、レイオフを経験し、現在は事業売却を検討している、とTech Crunchは報じた。
スタートアップの外部環境は険しくなっている。現在、恐ろしい技術の巨人の軍隊はより大きく、オンライン検索、ソーシャルメディア、デジタル広告、バーチャルリアリティ、メッセージングと通信、スマートフォンとホームスピーカー、クラウドコンピューティング、スマートソフトウェア、eコマースを含む幅広い分野で事業を展開している。
いくつかの例外がある。 Airbnb、Uber、Slack、およびその他の「ユニコーン」は、むしろ、既存企業との競争に直面している。しかし、彼らの数は少なく、多くのスタートアップはより達成可能な目標に照準を合わせることを学んだ。起業家はどの大企業が彼らを買収するかについて、ずっと早く考えるようになった。場合によっては創業前から検討し、買収されやすい企業を創業し、合流後に社内のラダーをうまく登ることまで考えている人すらいる。スタートアップの90%は、規模を達成するためではなく事業売却用に構築されている、と考える人すらいるほどだ。
キルゾーンとキラーアクイジションは、FTCの最も関心の高い問題です。FTCは2月、5社の大手テクノロジー企業(Alphabet、Amazon、Apple、Facebook、Microsoft)に特別注文を発行した。5社は、2010年1月1日から2019年12月31日までの間に行われた各取引の条件、範囲、構造、目的など、行ったすべての取引についてすべて報告する必要がある。これが業界の慣行に対しどの程度影響力があるのか、人々は注目している。
参考文献
- 渡辺安虎. IT規制導入へ行政に専門人材を 渡辺安虎氏. 日経新聞、2019/11/15
- C Cunningham et al. 2018. Killer Acquisitions
- Asher Schechter. Google and Facebook’s “Kill Zone”: “We’ve Taken the Focus Off of Rewarding Genius and Innovation to Rewarding Capital and Scale”. Pro-Market. May, 2018.
- James Pethokoukis. A new analysis takes a shot at the idea Big Tech has created a ‘kill zone’ for startups
- Oliver Wyman. Assesing the Impact of Big Tech on Venture Investment. July, 2018.
- Pitch Book. US VC Valuations Report. February 24, 2020.
- FTC. FTC to Examine Past Acquisitions by Large Technology Companies. February 11, 2020.





