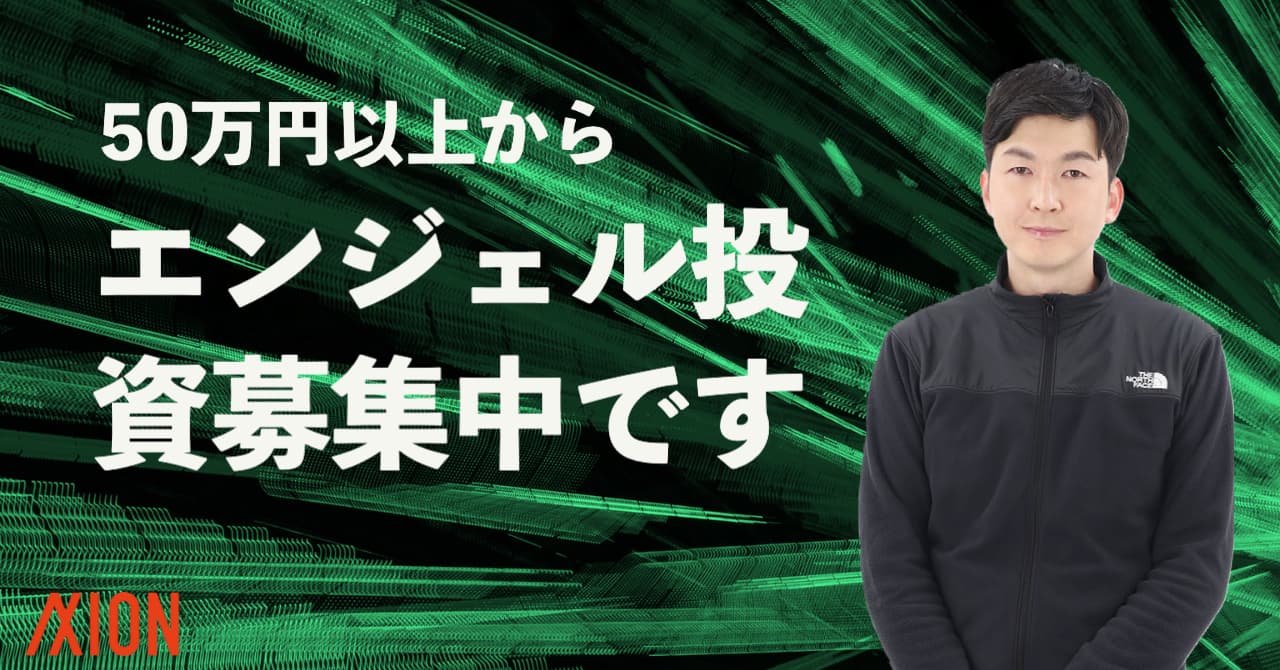半導体企業連合がArmをSBGから買収し中立化するシナリオ
半導体企業のコンソーシアム(共同企業体)がソフトバンクグループ(SBG)からArmを買収し中立化する可能性は否定できない。新規株式公開(IPO)の枯渇と景気後退観測は、SBGにIPO以外の選択肢を有望視させる可能性がある。

半導体企業のコンソーシアム(共同企業体)がソフトバンクグループ(SBG)からArmを買収し中立化する可能性は否定できない。新規株式公開(IPO)の枯渇と景気後退観測は、SBGにIPO以外の選択肢を有望視させる可能性がある。
チップメーカーのQualcommは最近、同社が昨年スタートアップのNuviaを買収した際に得た技術をもとに、Armサーバーチップ市場への再参入を準備していると報じられた。
Qualcommはモバイル向けのシステム・オン・チップ(SoC)において支配的な企業であるものの、CPUに関しては独自のノウハウに欠けていた。しかし、元Appleのチップデザイナーであるジェラルド・ウィリアムズらが、著名なCPUエンジニアとともに2019年に設立したNuviaのチームを得たことで、Qualcommは新しい力を手にすることになった。
AppleのM1の成功やAmazonやアリババなどのデータセンター向け独自Armチップの開発によって、Armの可能性は組み込みコンピュータからより広範な範囲へと広がった。
Qualcommは、同社の死活的な要所であるArm の株式を購入し、競争の激しい半導体市場で英国のチップ設計者の中立性を維持するコンソーシアムを作りたいと考えている。
QualcommのCEOであるクリスティアーノ・アモンは5月下旬、買収を行うコンソーシアムが「十分に大きい」場合、他のチップメーカーと手を組んでArmを完全に買収する可能性がある、とフィナンシャル・タイムズ(FT)に対して明らかにしている。「多くの企業が参加することで、Armが独立しているという正味の効果が得られるはずだ」と彼は言った。
これ以来、ソフトバンクグループ(SBG)がロンドン上場を見送ったという報道以外、Armの処遇を巡るニュースは乏しいため、水面下で交渉が行われている可能性も否定できない。
仮にArmが来年、米国上場を遂げた場合を仮定してみよう。おそらくArmの所有権には大きな「空き地」ができる、と想定できる。
SBGが少なくとも一定数のArm株を売ると予想されるためだ。ソフトバンクはマージンローン(証券担保融資)や株式先渡契約のような追加負債などを勘案すると、公に説明しているより、かなり高い水準の負債を抱えていると考えられる。また、SBGは今年の春にArm株を担保とした90億ドルの融資を受ける約束を取り付けたと報じられている。負債を償却するにはキャッシュが必要だ。
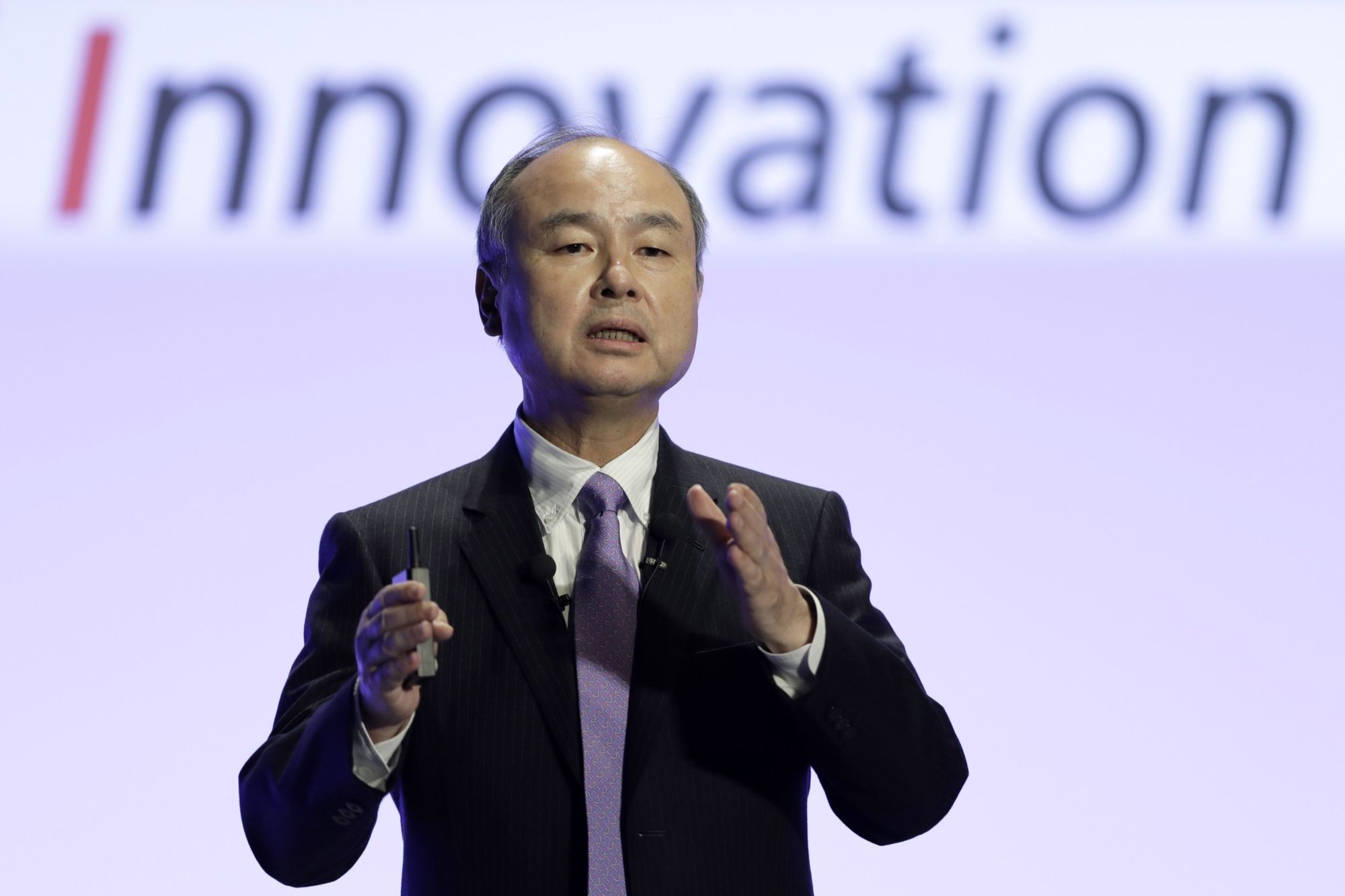
コンソーシアムの可能性
調査会社GlobalDataによると、世界最大のライバル半導体企業が連合して英国を拠点とするチップ設計会社Armを全面的に買収すれば、業界の様相が一変するという。
カリフォルニア州サンタクララを拠点とするNvidia社の400億ドルのArmへの入札は、各国当局の重圧で崩壊したが、コンソーシアムはそうした法的措置を回避できるだろう、とGlobalDataは述べている。
GlobalDataのテーマ別調査チームのコンサルタントアナリストであるMike Ormeは声明で、「これは、Intel、TSMC、Samsungが2012年にASMLに戦略的出資をして以来、半導体業界で最も重要な出来事となるかもしれない… その結果、ASMLは最先端の新世代のチップを作る手段を提供できる唯一の企業になりました」と述べている。「Arm技術が超低消費電力描画コンピューティングの青写真になることができれば、コンピューティングインフラのエネルギー需要とコストを根本的に削減することができます」
Intelのパット・ゲルシンガーは、2月に行われたロイターのインタビューで、同社がArmの買収計画に参加することに関心を示している。「もしコンソーシアムが出現すれば、おそらく何らかの形で参加することに非常に好意的だろう」と彼はロイターに語った。このようなコンソーシアムは、Nvidiaが2020年にArm買収の試みについて発表する以前から、静かに浮上していたとゲルシンガーは語っている。
NvidiaがArmを買収しそうになったとき、ライバルのチップメーカーは心配した。GPUの激しい競合相手で、なおかつAIに関連する技術のライセンス契約を支配することになるからだ。
SBGはArm株を担保にしたマージンローンの交渉時に500億〜600億ドルのバリュエーションを要求したとFTやブルームバーグは当時報じていた。しかし、IPOが枯渇し、世界的な景気減速が浮上しているいま、このようなバリュエーションは厳しいかもしれない。
このため、コンソーシアムが急襲してArmを買収する余地があるように思われる。SBGはキャッシュがほしいはずだ。そしてArmの背後をRISC-Vが急追してきている。


エンジェル投資を募集中
50万以上から投資可能です。次世代のニュースサービスの構築を支援しませんか? 詳細は以下の投稿のとおりです。